【徹底解説】フルトレーラーとは?種類・構造・運転のポイント・メリット
 フルトレーラーは、荷台が自立する構造を持つトレーラーで、大量輸送を効率的におこなえるのが特徴です。
フルトレーラーは、荷台が自立する構造を持つトレーラーで、大量輸送を効率的におこなえるのが特徴です。本記事では、フルトレーラーの構造や運転のポイント、導入メリットまで幅広く解説します。
目次
フルトレーラーとは?

フルトレーラーとは、荷重を自らの車体で支える構造を持つトレーラーで、単体でも安定して扱えるのが大きな特徴です。運転席やエンジンを備えるタイプもあり、自走が可能な車両も存在します。
けん引するトラクター側は荷重をほとんど受けないため、切り離せばトラクターを通常のトラックとして利用できます。
ここで整理しておきたいのが「トレーラー」と「トラクター」の違いです。トレーラーはエンジンを持たず、自力で走行できない車両の総称で、必ずけん引する車が必要です。
一方、トラクターはキャビンやエンジンを備え、トレーラーをけん引する役割を担う車両です。
フルトレーラーは、この組み合わせによって効率的な大量輸送を可能にし、物流の現場で広く活用されています。
セミトレーラーとの違い
フルトレーラーとセミトレーラーの主な違いは、その構造と運転操作にあります。フルトレーラーは前後または中央に車軸があり、荷台を含むトレーラー部分が単体で自立できる点が特徴です。連結するトラクターは、トレーラーの荷重を支える必要がなく、牽引する役割に専念します。フルトレーラーのトラクターは、一般的なトラックに連結機能が追加された「フルトラクター」と呼ばれています。
一方、セミトレーラーは、トレーラー前部に車輪がないため、前側の荷重を自ら支えられません。そのため、トラクターがその荷重の一部を支えながら牽引する構造となっています。セミトレーラーのトラクターは、荷台のない「トラクターヘッド」と呼ばれる車両です。
フルトレーラーの寸法
フルトレーラーの寸法は道路運送車両法で定められており、一般的な基準は全長18m、全幅2.5m、全高3.8m以内とされています。これは特殊な許可を受けない通常の運行で適用される基準値です。
しかし、ドライバー不足や物流効率化の要請を背景に規制緩和が進められており、現在では一定の条件を満たすことでより長い車両の運行が可能となっています。
2019年の法改正では、バン型フルトレーラー連結車は最大25mまで認められるようになりました。ただし、25mの運行が許されるのは高速道路や自動車専用道路など条件が整った区間に限られ、一般道を走行する際には道路管理者の許可が必要です。
フルトレーラーの構造
フルトレーラーは、構造や連結方法によって「ドリー式フルトレーラー」と「センターアクスル式フルトレーラー」に分類されます。
それぞれのトレーラーの違いについて解説します。
1.ドリー式フルトレーラー

(画像引用元:東邦車輛株式会社)
ドリー式フルトレーラーは、ドリーと呼ばれる回転式の台車をもつフルトレーラーです。このドリーは、回転機能を持つため、トラクターとトレーラーの動きをスムーズに連動させ、荷重を分散する役割を果たします。前輪と後輪が離れて配置されていることで安定性が高く、重量物の長距離輸送にも適しています。
一方で、トラクターとドリー、ドリーとトレーラーという2か所の連結部を持つため操縦は複雑になり、特にバック時や狭い場所での操作には高度な技術が求められます。連結を外しても自立可能な点は利便性が高いものの、運転には慣れが必要とされる種類のフルトレーラーです。
2.センターアクスル式フルトレーラー

(画像引用元:東邦車輛株式会社)
センターアクスル式フルトレーラーは、車軸が荷台の中央付近に配置され、前方に伸びたドローバー(連結棒)でトラクターと接続する構造を持ちます。ドリー式のように折れ曲がる部分がないため、運転感覚はセミトレーラーに近く、比較的扱いやすいのが特徴です。連結部がシンプルな構造のため、トラクターとの隙間が小さくなり、その分荷台を長く確保できるメリットがあります。
また、中央に車軸が集まっていることから荷重バランスが良く、エアサスペンションなどを備えた車両では安定性も高まり、荷崩れのリスクを軽減できます。
フルトレーラー車体の種類
フルトレーラーには、荷台の形や運ぶ荷物の種類に応じて、下記の4種類にわけられます。
| 1.平ボディ 2.バン 3.ダンプトレーラー 4.ライトトレーラー |
それぞれの特徴について解説します。
1.平ボディ
平ボディは、荷台に屋根がないオープンタイプで、フルトレーラーだけでなく、様々な種類のトラックに採用されています。荷台の後方と側方にはアオリと呼ばれるパネルがついており、上から荷物を積み下ろすことが可能です。
屋根付きの車両に比べて車両重量が軽いため、より多くの荷物を積載できるというメリットがあります。重量物や長尺物、あるいは形状の異なる多様な荷物の積載に適しており、汎用性の高さから多くの場面で活躍します。
2.バン
バンタイプのフルトレーラーは、荷台が箱型になっており、荷物を雨風や盗難から保護できるというメリットがあります。貨物室が密閉されているため、食品や精密機器など、外部環境からの影響を受けやすい貨物の輸送に特に適しています。
側面が大きく開閉するウイングタイプもあり、荷物の積み下ろし作業の効率を向上させることが可能です。
3.ダンプトレーラー
ダンプトレーラーは、荷台をリフトアップして積載物を一気に排出できる構造を持つトレーラーです。トラクターがけん引する荷台部分にリフト機構が備わっており、大量の荷物を効率的に積み下ろしできるのが大きな特徴です。
建設現場では砂利や砕石の運搬に、また廃棄物処理場では産業廃棄物やゴミの輸送に活用されるなど、用途は幅広くあります。積載量は18トン前後と大きく、短距離で大量の資材を移動する場面で力を発揮しますが、重量が増すほど転倒のリスクも高まるため、使用環境や操作には注意が必要です。
4.ライトトレーラー
ライトトレーラーは、キャンピングトレーラーやボートトレーラーなどの比較的軽量なトレーラーの通称です。ライトトレーラーは、主にセンターアクスル式のフルトレーラーが多く見られます。
エンジンを持たず、単体で自走はできませんが、自動車に牽引されることを前提として製造されています。連結装置も小型で簡易的なため、キャンピングトレーラーなどの個人レジャー目的で利用されることが多いです。
フルトレーラーの代表的なメーカー
フルトレーラーの代表的なメーカーとしては、東邦車輛株式会社、日本トレクス株式会社、日本フルハーフ株式会社、株式会社浜名ワークスなどが挙げられます。これらのメーカーは、それぞれ特色あるフルトレーラーを製造しています。
例えば、日本トレクスは、バンフルトレーラーや粉粒体運搬フルトレーラー、コンテナ積載フルトレーラーなどを手掛けています。また、日本フルハーフは、センターアクスル式のフルトレーラーのほか、ドライバンやウイングルーフ、温度管理バンといった幅広い架装を取り扱っています。
フルトレーラーのメリット

フルトレーラーのメリットは、下記の3つです。
| 1.最大10トントラック2台分の輸送がおこなえる 2.人件費の削減とドライバー不足の解消 3.自動車重量税が非課税 |
それぞれのメリットを紹介します。
メリット1:最大10トントラック2台分の輸送がおこなえる
フルトレーラーの大きなメリットは、一度に大量の荷物を運べる点です。通常のトラックであれば2回に分けて運ぶ必要がある荷物でも、フルトレーラーを使えば一度の運行でまとめて輸送できます。
例えば、ドライバー1人で最大10トントラック2台分に相当する貨物を運ぶことが可能です。
大量の荷物を運べることによって、他のトレーラーとの連結や中継拠点を活用した輸送も可能で、物流計画の柔軟性が高まるというメリットもあります。
メリット2:人件費の削減とドライバー不足の解消
フルトレーラーは、一度に大量の荷物を運べるため、輸送回数を大幅に減らすことが可能です。これにより、必要なドライバーの人数を抑えられるため、人件費の削減に直結します。
また、少子高齢化や労働力不足が進む中、トラック運送業界ではドライバーの確保が大きな課題となっています。フルトレーラーを活用すれば、一人のドライバーで通常の複数台分の荷物を運べるため、人手不足の緩和にもつながります。ただし、高度な運転技術が求められるため、経験あるドライバーの確保が重要です。
メリット3:自動車重量税が非課税
フルトレーラーの大きなメリットの一つは、トレーラー部分が自動車重量税の課税対象外であることです。トラクターには重量税がかかりますが、トレーラー部分はエンジンを持たないため非課税となります。そのため、トラック1台分の積載能力を持ちながらも、税金負担を抑えることが可能です。
複数のトレーラーを牽引しても、トラクター1台分の重量税だけで済むため、輸送効率を高めつつ経費削減にもつながります。人件費や燃料費と並び、重量税の軽減は運送業にとって大きなコストメリットとなり、フルトレーラーの導入を検討する理由のひとつとして注目されています。
フルトレーラーは導入コストがかかる?

フルトレーラーは輸送効率の向上が期待できる反面、導入時には車両価格などのコストがかかります。新車のフルトレーラーの価格相場は1,500万円から2,000万円程度と、一般的な大型トラックの新車価格とほぼ同じか、それ以上の費用がかかる場合があります。
そのため、導入コストを抑えたい場合は、新車ではなく中古での購入を検討することをおすすめします。中古のフルトレーラーは100万円程度から購入できるものもありますが、年式や走行距離、車種、架装内容によって価格は大きく異なります。
導入コストを抑えるためには、中古車両の購入以外にも、リース契約の検討も有効な手段です。
フルトレーラーの購入は「トラック流通センター」へ
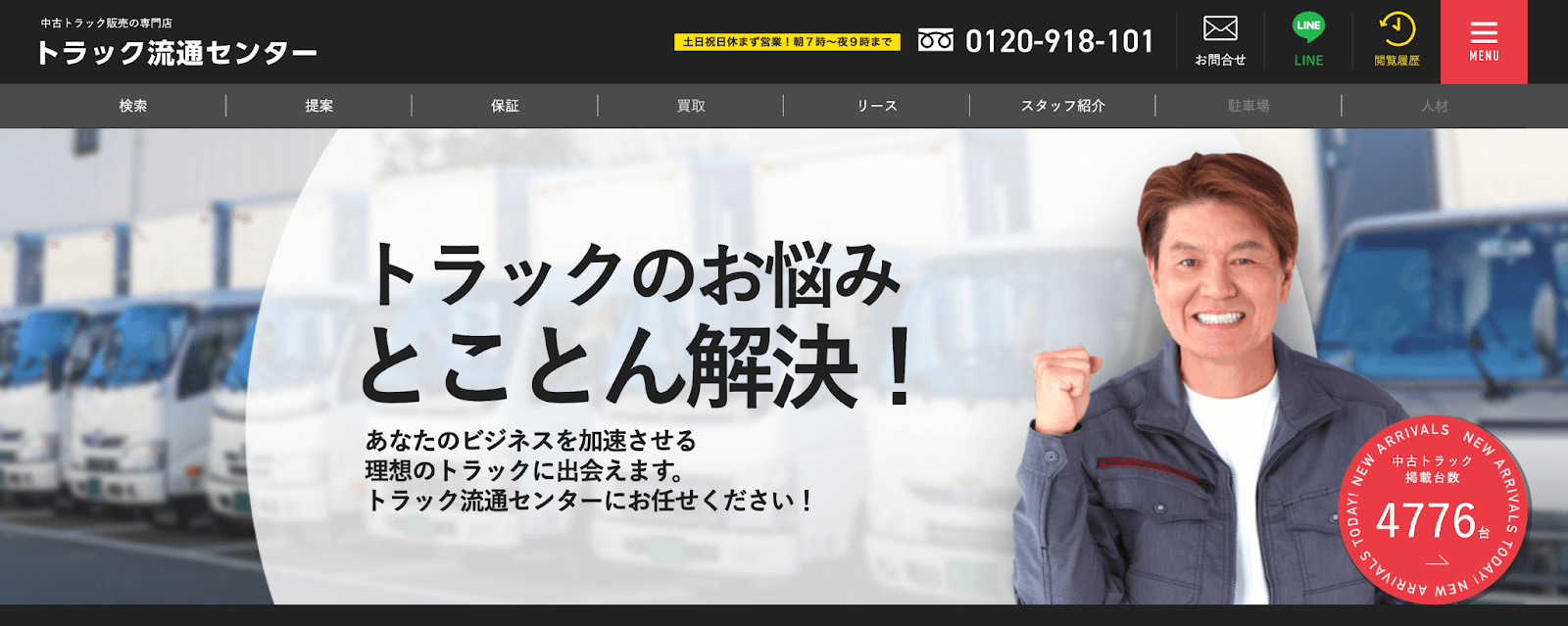
フルトレーラーの購入を検討されている方は、トラック流通センターをご利用ください。豊富な車種の中から、お客様のニーズに合ったフルトレーラーを見つけられるでしょう。専門知識を持ったスタッフが、車両選びから購入手続きまで、きめ細かくサポートいたします。
フルトレーラー運転ポイント(運転のコツ)
フルトレーラーの運転は、全長が長く連結部分があるため、通常のトラックとは異なる独特の難しさがあります。特にバックやカーブ、車庫入れといった操作は、高い運転技術と経験が求められます。
ここでは、フルトレーラーの運転のコツについて紹介します。
1.バック
フルトレーラーをバックする際は、トレーラーを動かしたい方向とは逆にハンドルを切ることが基本です。例えば、左に曲がりたい場合は右にハンドルを回しながら下がることで、車両全体が左に折れて曲がります。
ただし、車両構造によって操作方法は異なります。センターアクスル式は連結部が1か所のためセミトレーラーに近い感覚で操作できますが、ドリー式は連結部が2か所あるため、曲げたい方向にハンドルを回すイメージでおこないます。
いずれの場合も小刻みに操作し、窓を全開にして死角を確認することが重要です。最後尾は死角になりやすいため、必要に応じて車を降りて確認することで、安全にバックすることが可能です。
2.カーブ
フルトレーラーでカーブを曲がる際は、大きな内輪差に特に注意が必要です。トレーラーの全長が長いため、右カーブでは後輪が道路内側に寄りやすく、左カーブではトレーラー前部が外側にはみ出す場合があります。
そのため、曲がる前に十分に減速し、大きめの軌道を描くようにハンドル操作をおこなうことが重要です。内輪差を意識しながら徐々に曲がることで、安全に通行できます。
また、夜間や山間部など見通しが悪い場合は、対向車や障害物に特に注意してください。フルトレーラーの長さや幅を理解し、慎重にカーブを回ることで事故防止につながります。
3.車庫入れ
フルトレーラーの車庫入れは、その全長と連結構造から非常に難しい操作の一つです。
真っ直ぐ後退しているつもりでも、トラクターとトレーラーのずれによって車体が曲がってしまう現象がよく起こります。
このような場合、ずれた方向にハンドルを切り、トレーラーとトラクターを一直線にするように修正します。一直線になったら、今度はハンドルを反対に切り、トレーラーが目標のラインに合うように戻しましょう。ラインにトレーラーが合致したら、ハンドルを戻していくことで修正が完了します。
フルトレーラーの車庫入れは、一度で完璧に入れようとせず、何度か切り返すことを前提におこなうのが成功のコツです。無理な操作を避け、確実な手順で車庫入れをおこなうことが事故防止に繋がります。
フルトレーラーに関するよくある質問
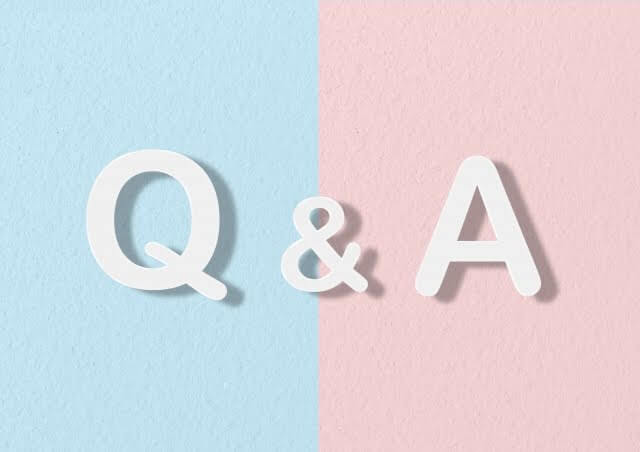
フルトレーラーに関するよくある質問をまとめました。
フルトレーラーの運転は難しい?
フルトレーラーの運転は、セミトレーラーと比較して難易度が高いとされています。これは、トレーラーの全荷重が後方の接続部分にかかるため、車両全体の取り回しやカーブを曲がる際の操作がより複雑になるためです。フルトレーラーはセミトレーラーよりも全長が長いため、運転には繊細な操作が求められます。
フルトレーラーの運転に必要な免許は?
フルトレーラーの運転には、「大型免許」と「牽引免許」の両方が必要です。大型免許は、車両総重量11トン以上や最大積載量6.5トン以上の車両を運転する際に求められます。フルトレーラーは非常に重く長いため、普通免許や中型免許では運転できません。
また、けん引免許(けん引第一種免許)は、車両総重量750kgを超えるトレーラーをけん引する場合に必須です。フルトレーラーはトラクターで重いトレーラーを牽引する構造のため、この免許も必ず必要です。これらの免許は取得難易度が高く、教習所での専門的な訓練や実技練習が重要です。
ダブル連結トラックとは?
ダブル連結トラックは、大型トラックの後部にさらにフルトレーラーを連結した特殊な車両で、全長は最大25メートルまで可能です。これにより、通常の大型トラック2台分に相当する積載量を、1台で運べます。
トラクターとトレーラーそれぞれに独立した荷台を持つため、荷物を効率よく分けて積載でき、輸送の自由度も高まります。
2019年の規制緩和により、長さの上限が21mから25mに拡大されたことで、より長距離輸送や大量貨物の運搬が可能になりました。この構造は、輸送効率の向上やドライバー不足の解消、省人化、さらにはCO2排出量の削減など、物流の多くの課題に対応する手段として注目されています。
<あわせて読みたい>
さまざまな種類で大量輸送を実現する牽引貨物自動車!トレーラーを一挙に大紹介!
まとめ
連結全長の規制が緩和されるまで国内で運行するトレーラーはセミトレーラーが中心でしたが、最大25mまで連結全長が緩和された現在以降、フルトレーラーのダブル連結トラックへのニーズが高まることが予想されます。輸送効率を最大100%増加させられるフルトレーラーのダブル連結トラック導入のポイントである次の3つに留意しながら、フルトレーラー導入で大きな経済効果を手に入れてみてはいかがでしょうか。
-
- フルトレーラーは、荷重を自らの車体で支える構造を持つトレーラーで、単体でも安定して扱えるのが大きな特徴
- フルトレーラーとセミトレーラーの違いは、トラクターを含めた車両全体の構造と、バック時のハンドル操作
- ルトレーラーは、「ドリー式フルトレーラー」と「センターアクスル式フルトレーラー」の2つのタイプに分けられる。






