増トントラック(増トン車)とは?積載量・寸法・免許・価格・メリット

増トントラックは、4トントラックをベースに車体を強化し、積載量を増やした中型トラックです。大型に近い積載力を持ちながら、扱いやすいサイズで効率的な運搬が可能です。
本記事では、増トントラックの特徴や免許、メリットデメリットをわかりやすく解説します。
目次
増トントラック(増トン車)とは?

増トントラック(増トン車)とは、一般的に4トントラックをベースに、シャーシなどを強化することで最大積載量を増加させたトラックのことです。シャーシやフレームを強化することで、5トンから6.5トン未満、あるいは8トンまで積載できるようになります。
これは、2007年の道路交通法改正により、中型トラックの車両総重量の上限が引き上げられたことで可能になりました。大型トラックに近い積載量を持ちながら、中型トラックのサイズ感を維持しているのが特徴です。
これにより、一度に多くの荷物を運ぶことが可能になり、輸送効率の向上につながります。
増トントラックと中型トラックとの違い
増トントラックと中型トラックの大きな違いは、最大積載量です。標準的な4トントラックの積載量に対し、増トントラックはフレームや車軸を強化することで6トンや8トンなど、より多くの積載を可能にしています。
外見上は似ていますが、車両後部に記載された最大積載量を確認するのが最も確実な見分け方です。また、ホイールのボルトの数も違いの一つで、通常6個の中型トラックに対し、増トントラックは8個の場合が多いです。
さらに、タイヤがやや大きめのサイズに変更されサイドバンパーが増設されているほか、サイドミラーにはアンダーミラーが追加されているなどの細かい見分け方もあります。
増トントラック寸法(サイズ)・積載量

増トントラックは、ベースとなるトラックの種類によって積載量や寸法が異なります。
主に4トントラックをベースにした車両では、積載量が5トンから6.5トン未満、車両総重量が8トンから11トン未満となることが多いです。
6トントラック寸法(サイズ)・積載量
6トントラックは、主に4トントラックをベースに積載量を増やした増トン車です。積載量は5.4トンから6.3トン程度です。荷台寸法は4トントラックと大きな差はありませんが、全長、全幅、全高などの車両全体のサイズは、メーカーによって多少異なります。
一般的なサイズは、全長8,350mm、全幅2,330mm、全高3,450mmが目安とされています。これらのサイズと積載量により、中型トラックながらより多くの荷物を運搬することが可能です。
8トントラック寸法(サイズ)・積載量
8トントラックのサイズや積載量は、メーカーや車種によって異なります。平均的な目安としては、最大積載量は約8トン、車両総重量は約13トンから15トン程度です。全長は約7.2メートルから10.4メートル、全幅は約2.2メートルから2.5メートル、全高は約2.5メートルから2.9メートルです。
サイズは、平ボディ、ウイング、ダンプなど荷台の種類によっても変わります。例えば、平ボディでは荷台長約6.5メートル、荷台幅約2.5メートル程度のものがあります。
購入や利用の際には、用途に合わせて詳細な寸法や積載量を確認することが重要です。
増トントラックのメリット・デメリット
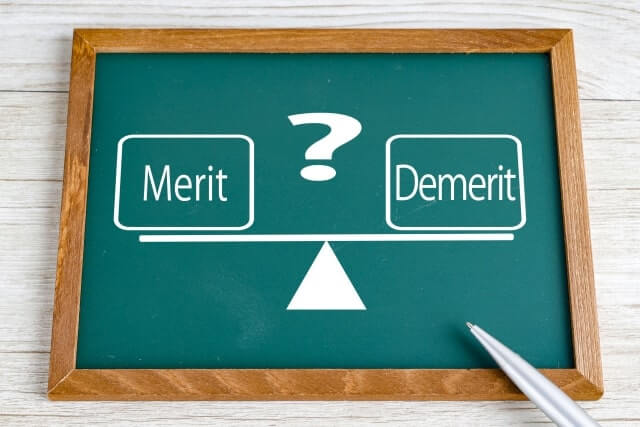
増トントラックは、通常の4トントラックに比べて積載量が増やせるため、効率的な輸送が可能になる車両です。
しかし、その一方で、導入や運用にあたって注意すべき点もあります。ここでは、増トントラックの主なメリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説します。
増トントラックのメリット
増トントラックは、最大積載量が増やせる以外にも、下記のメリットが存在します。
| 1.車両コスト、ランニングコストを抑えられる 2.中型免許で運転できるケースがある 3.大型トラックよりも小回りが利く |
それぞれのメリットについて解説します。
1.車両コスト、ランニングコストを抑えられる
増トントラックは、大型トラックと比較して、初期の車両価格を抑えられきます。
例えば、大型トラックが1,200万円から1,500万円程度なのに対し、増トントラックは200万円から600万円と相場より安価に購入可能です。
また、維持費用も大型トラックより低く抑えられる傾向があります。特に、車両総重量に応じた自動車重量税は、増トンしても大型トラックより安くなります。また、タイヤ交換費用や保険料なども、大型トラックに比べてコストを抑えることが可能です。このように、増トントラックは大型トラックと比較して、コスト効率良く運搬量を増やせる点がメリットです。
2.中型免許で運転できるケースがある
増トントラックは、車両総重量や最大積載量によって、中型免許で運転できる場合があります。一般的な4トントラックをベースに積載量を増やした増トントラックは、車両総重量が8トンから11トン未満、最大積載量が5トンから6.5トン未満であることが多く、この範囲内であれば中型免許で運転可能です。
これにより、大型免許の取得にかかる費用や時間を抑えられるというメリットがあります。ただし、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の増トントラックでは、大型免許が必要となるため、運転するトラックの種類や積載量を確認することが重要です。
3.大型トラックよりも小回りが利きやすい
増トントラックは、大型トラックに比べて車両サイズがコンパクトな点も大きなメリットです。これにより、狭い道や住宅街、山道など、大型トラックでは通行が難しい場所でも比較的スムーズに走行できます。
また、最小回転半径が小さいため、駐車や方向転換の際にも小回りが利きやすく、運転の負担軽減に繋がります。大型トラックと比較して、駐車場の選択肢が広がることも利点です。
増トントラックのデメリット
増トントラックには、下記のデメリットが存在します。
| 1.中型(4トン)トラックよりコストがかかる 2.中型免許以上の取得が必要 3.運転難易度が高く、技術が必要 |
それぞれのデメリットについて解説します。
1.中型(4トン)トラックよりコストがかかる
増トントラックは、大型トラックと比較するとコストが安くなりますが、4トンクラスの中型トラックと比較するとコストがかかる点がデメリットです。
たとえば、高速道路の料金区分が大型車と同じになる点が違いとして挙げられます。車両総重量が8トン未満の中型トラックは高速道路料金が中型車料金ですが、増トントラックは8トン以上となるため大型車料金が適用されます。
2.中型免許以上の取得が必要
増トントラックを運転するには、車両の総重量に応じて中型免許または大型免許が必要です。2007年の法改正により中型免許で運転できるトラックの範囲が広がりましたが、8トンを超える増トントラックの場合は、大型免許が必要になります。
ご自身の免許で運転できる増トントラックの車両総重量を確認し、必要であれば中型免許以上の免許取得を検討しましょう。免許なしで運転すると無免許運転となり、罰則の対象となりますので注意が必要です。
3.運転難易度が高く、技術が必要
増トントラックは、通常の4トントラックに比べて車両総重量が増加するため、運転にはより高度な技術が求められます。特に、積荷の重量が増えることで、ブレーキの制動距離が長くなる傾向があり、カーブや悪路での安定性には注意が必要です。
また、車両サイズによっては通行できない道路もあるため、事前の経路確認が重要となります。これらの理由から、増トントラックの運転は4トントラックよりも難易度が高く、経験に裏打ちされた運転技術が必要とされます。
増トントラックの運転に必要な免許

増トントラックを運転するには、車両総重量や最大積載量に応じて中型免許または大型免許が必要です。
2007年の法改正により中型免許で運転できる範囲が広がりましたが、車両総重量11トン以上や最大積載量6.5トン以上のトラックには大型免許が求められます。
それぞれの免許区分で運転できる増トントラックを下記の表にまとめました。
| 免許区分 | 最大積載量 | 車両総重量 | 増トン車の例 |
| 準中型免許 | 〜4.5t | 〜7.5t | 対象外 |
| 中型免許 | 〜6.5t | 〜11t | 6t車など |
| 大型免許 | 制限なし | 8t車など | |
増トントラックを運転する前に、ご自身の免許で運転できる増トントラックの範囲を車検証で確認することが重要です。
中型免許で運転する場合
増トントラックを運転するには、原則として中型免許以上の運転免許が必要です。現在、中型免許で運転できるトラックは、車両総重量が11トン未満、最大積載量が6.5トン未満となります。
増トントラックは、この中型免許の範囲内でより多くの荷物を積載できるように改造されています。しかし、車両総重量が11トンを超える増トントラックを運転する場合は、大型免許が必要となりますので、注意が必要です。
大型免許で運転する場合
増トントラックを大型免許で運転する場合、主に8トンクラスの車両が該当します。これらのトラックは車両総重量が11トンを超えるため、大型免許が必要となります。
大型免許を取得することで、より多くの積載量を持つ増トントラックの運転が可能になり、仕事の幅を広げられます。しかし、車両のサイズや重量が増すため、運転にはより慎重さが求められます。
おすすめメーカー・車種|増トントラック
増トントラックは、近年中古車市場でも多くの車両が見られるようになりました。
主なメーカーと車種は、下記のとおりです。
| メーカー | 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | 特徴 |
| 三菱ふそう | ファイター | 851cm | 228cm | 267cm | 長い歴史をもち、安全装備や燃費性能が強み |
| いすゞ | フォワード | 818cm | 227cm | 275cm | 燃費性能や安全性能に優れており、様々な種類の完成車がラインナップ |
| 日野 | レンジャー | 891cm | 234cm8 | 339cm | エンジンの軽量化に加え、馬力と燃費を高次元で両立 |
| UDトラックス | コンドル | 685cm | 235cm | 259cm | 環境性能と燃費効率を両立するエンジンを採用し、先進安全機能を備える |
それぞれの増トントラックについて紹介します。
1.三菱ふそう:ファイター
三菱ふそうのファイターは、中型トラックとして長い歴史を持つモデルです。1984年にFKシリーズから名称変更され誕生しました。ファイターという名前には「戦士」という意味が込められています。
現行モデルは2代目で、安全装備や燃費性能が向上しています。積載量を増やした増トン仕様もラインナップされており、幅広いビジネスに対応する三菱ふそうを代表するトラックの一つです。
2.いすゞ:フォワード
いすゞ自動車が製造する中型トラックのフォワードは、1970年に初代が誕生し、2023年には6代目が登場するなど、長年にわたり進化を続けているトラックです。燃費性能や安全性能に優れており、車両総重量8トンから11トンクラスで高い販売実績を誇ります。
ウイングや冷凍車など、様々な種類の完成車がラインナップされています。増トン仕様もあり、幅広いニーズに対応していることが特徴です。エンジンは、高い環境性能と燃費性能を実現したD-COREなどが搭載されています。
3.日野:レンジャー
日野自動車が手がける中型トラック、レンジャーは多様なニーズに対応するモデルです。4トンクラスから8トンクラスまで、幅広い種類のラインアップが用意されています。特に、積載量4トンクラスのトラックは、増トンのベース車両としても多く選ばれています。
レンジャーは、A05Cエンジンを搭載しており、エンジンの軽量化に加え、馬力と燃費を高次元で両立させているのが特徴です。燃費性能の向上にも力が入れられており、平成27年度燃費基準+5%を達成しているモデルもあります。
4.日産UDトラックス:コンドル
日産UDトラックスのコンドルは、中型トラックとして長い歴史を持つモデルです。かつては日野自動車との提携により、日野製のエンジンを搭載していた時期もありました。
その後、自社製のエンジンに戻り、環境性能と燃費効率を両立するエンジンを採用しています。現在のコンドルは、いすゞ自動車からのOEM供給を受けており、最新のエンジンと先進安全機能を備えています。
乗り換えするなら中古トラック市場の増トントラック

増トントラックへの乗り換えを検討しているなら、中古トラック市場の活用がおすすめです。新車と比べて価格を抑えられるだけでなく、構造変更がすでに施された増トントラックも多く、スムーズに導入できる点が魅力です。また、中古市場には三菱ふそう・いすゞ・日野など主要メーカーの車種が豊富に流通しており、用途や業種に応じた最適な一台を見つけやすくなっています。コストを抑えつつ輸送効率を高めたい方にとって、中古の増トントラックは非常に有力な選択肢です。
増トントラックを中古で購入する際の注意点
中古の増トントラックを購入する際は、価格だけで判断せず、車両の状態をしっかりと確認することが大切です。増トントラックは一般的な4トントラックに比べて積載量が多く、より過酷な環境で使用されていることが多いため、走行距離だけでは判断できない消耗が進んでいるケースもあります。特にエンジンやミッション、サスペンションなどの主要部品に異常がないか、現車でのチェックは欠かせません。
また、過去のメンテナンス履歴が残っているかどうかも重要なポイントです。整備の記録があれば、車両の使用状況や不具合の有無を把握しやすくなり、安心して導入できます。さらに、荷台や荷室の傷・腐食・塗装の状態も確認し、日常的な使用に支障がないかを見極めましょう。
ナビやパワーゲートなどの装備類が正常に動作するかも、快適な運用に関わる要素です。装備に不具合があると後から修理費用が発生する可能性があるため、事前のチェックが重要です。これらのポイントを押さえることで、コストを抑えながらも品質の高い中古増トン車を見つけることが可能です。
増トントラックの購入は「トラック流通センター」がおすすめ

中古の増トントラックを購入したいときは、トラック流通センターの利用がおすすめです。全国の在庫車両をオンラインで一括検索でき、希望の条件に合ったトラックを効率的に探せます。
掲載車両には、年式・走行距離・車検の有無・価格などの詳細情報を明記しており、比較検討のしやすさが強みです。
また、専門スタッフによるサポート体制も万全です。トラックの選定や購入に関する疑問にも丁寧にお答えしています。
<増トントラック(増トン車)の在庫をみる>
<かんたん問い合わせ>
<とことん提案>
もちろん、現車確認や試乗対応、ローン・リースの相談も可能です。与信に自信がない方にも、提携しているローン・リース会社をご紹介します。この機会にご検討ください。
増トントラックに関するよくある質問

増トントラックに関して、よくある質問をまとめました。
使用中のトラックは増トン可能?
現在使用している4トントラックを「増トントラック」に改造することは可能です。
まず、増トンを実現するにはシャシーやサスペンションなどの主要部品を補強し、車両が増加した積載量に耐えられるように構造を強化する必要があります。
このような改造には専門業者による施工が必要で、数週間から数ヶ月の期間と相応の費用がかかるのが一般的です。
一見すると、新車を購入するよりもコストを抑えられる選択肢に思えますが、改造の際にはメーカー保証が無効になるケースも多く、万一のトラブル時には自社での対応が求められる場合もあります。特に事故時の責任問題などについても、あらかじめ理解しておくことが大切です。
また、すべてのトラックが増トン改造に適しているわけではありません。比較的新しい車両であれば強度的に改造に耐えられる可能性がありますが、年式が古くシャシーの劣化が進んでいる車両では、安全面から施工を断られることもあります。増トン改造を検討する場合は、まず改造業者に車両の状態(年式・走行距離・修復歴など)を伝え、施工の可否を確認することが重要です。
トラックの増トンは構造変更手続きが必要?
範囲外や車検証記載内容の変更に関する改造をおこなうと、大規模改造に該当します。そのため、構造変更手続きが必要となります。二次架装の基準となる一定範囲は、次のとおりです。
|
・全長の変化:±3cm以内 |
二次架装は、軽微な変更として扱われるため特に手続きが必要となるものではありません。しかし、二次架装の範囲内で収まっていなければ違法改造となる可能性があるため、陸運支局や整備工場での確認をおすすめします。
構造変更手続きの流れは、次のとおりです。
|
①陸運支局に構造変更手続きと構造変更検査の予約をおこなう |
構造変更手続きに必要な書類は?
増トントラックに改造すると、陸運支局で構造変更手続きをしてから構造変更車検を通過する必要が生じます。
提出が求められる必要書類は、次のとおりです。
|
・陸運支局で用意されている構造変更申請書 |
増トントラック運転時の注意点は?
増トントラックを運転する際には、積載力ゆえに運転に独特の感覚が求められます。
特に注意すべき点は、以下の2点です。
| ①制動距離 ②横転リスク |
1点目は、制動距離です。積載量が増えることで車両の総重量が大きくなり、ブレーキをかけてから完全に停止するまでの距離が長くなります。これまでと同じタイミングでブレーキを踏んでも止まりきれないことがあるため、スピードを控えめにし、早めの減速を意識した運転が重要です。
2点目は、横転のリスクです。車高が高く重心が上がるため、横風やカーブ、高速走行時には車体がふらついたり、最悪の場合は横転する可能性もあります。特に風の強い日や高速道路での運転時は、スピードを落とし、慎重にハンドル操作をおこなう必要があります。
安全な走行のためには、車両の重さや特性を理解し、より慎重な運転を心がけましょう。
増トントラックはどんなシーンで活躍する?
増トントラックは、さまざまな現場でその積載力と機動性を活かして活躍しています。
代表的なのは、定期便や物流センター間の輸送です。一定量の荷物を安定して運ぶ必要がある配送業務では、積載効率が高くかつ燃費や運行コストを抑えられる増トントラックが重宝されています。
また、建築現場や資材運搬の現場でもその力を発揮します。重量のある建築資材や大型機材を効率よく運ぶ必要があるため、非常に適しています。車両サイズも中型〜大型の中間に位置するため、都市部や現場近くへの乗り入れも比較的しやすく、柔軟な運行が可能です。
「中型トラックでは物足りない」「大型は大きすぎる」といった場面で選ばれることが多く、中間的な輸送ニーズに応える車両として、幅広い業種で活躍しています。
まとめ
増トントラックは、中型トラックのサイズ感で大型トラックに近い積載量を実現できるため、輸送効率の向上に貢献します。導入時には、車両総重量や最大積載量によって必要となる運転免許の種類が異なる点に注意が必要です。新たな増トントラックの導入を検討する際は、中古トラック販売店を利用することで費用を抑えられる可能性があります。
-
- 増トン車は中型クラスの車両区分で大型クラスに迫る積載量を実現
- 増トン車の運転資格には中型免許以上の免許区分が求められる
- 増トントラック導入は中古トラック販売店の利用がおすすめ






