ラフタークレーンのサイズやメーカーは?|必要な免許・トラッククレーンの違い
 ひと口に「クレーン」といっても種類がいくつかあり、トラックに備え付けられたクレーンは小型のものから大型のものまであります。どのような違いがあるか詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
ひと口に「クレーン」といっても種類がいくつかあり、トラックに備え付けられたクレーンは小型のものから大型のものまであります。どのような違いがあるか詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
本記事は、ラフタークレーンに焦点を当て、その特徴やサイズ、主要メーカーについてご紹介します。また、トラッククレーン(ユニック車)との違いや、それぞれの運転・操作に必要な免許についても解説します。
ラフタークレーンとは?

ラフタークレーンとは、不整地や狭い場所でも優れた走行性を持つ移動式クレーンです。ラフテレーンクレーンとも呼ばれています。ラフタークレーンは、ホイールクレーンの一種であり、一つの運転席で走行とクレーンの操作が可能なため、効率的な作業が可能です。
また、ラフタークレーンは、操向機構にも独自の特徴があります。大型タイヤを備えた全輪駆動式のため、不整地ややわらかい地盤でも安定して走行可能です。さらに、4つの操向モードを搭載しており、限られたスペースでも高い機動力を発揮します。
ラフタークレーンのサイズ
ラフタークレーンは吊り上げ荷重を基準に、主に「小型(ミニ)ラフター」「汎用ラフター」「追加ウエイト付きラフター」の3種類に分類されます。それぞれのラフタークレーンの種類を紹介します。
小型ラフタークレーン
小型ラフタークレーンは、4.9tから16t程度の吊り上げ荷重に対応し、主に狭い場所やビルの3〜4階程度の高さの作業に適しています。
例えば、5tや8tのラフタークレーンはコンパクトで小回りが利き、市街地や狭い公道での作業に活躍します。また、16tクレーンでも狭い道路を通行でき、3〜4階の建物での作業に適しています。
汎用ラフタークレーン
汎用ラフタークレーンは、20tから70トン程度までの吊り上げ荷重に対応しており、小型ラフターよりも高所での作業が可能です。
25tクレーンは大型工事現場で活躍し、20tクレーンよりも高い場所への吊り上げが可能です。20tを超えるラフタークレーンが公道を走行する際には、特殊車両通行許可の取得が必要です。しかし、20tラフタークレーンは自重が20t未満のため、この許可が不要で、すぐに作業に取り掛かれる利点があります。
追加ウエイト付きラフタークレーン
追加ウエイト付きラフタークレーンは、80t以上の吊り上げ荷重に対応しています。アウトリガーに加えてウエイトを取り付けることで車体を安定させ、重い荷物を吊り上げても横転しにくいのが特徴です。これにより、ビル15階相当の高所まで重量物を吊り上げることが可能です。
ただし、このウエイトを付けたままでは、公道を走行できません。特に、世界最大級の145tクラスのラフタークレーンは、港湾やプラントといった限られた現場で活躍するケースが多く、公道を移動する場合はクレーン部やブーム部を分解する必要があります。
ラフタークレーンのメーカー・モデル
ラフタークレーンの導入を検討する際には、メーカーとモデル選びが重要です。ここでは、ラフタークレーンの主要なメーカーである「コベルコ建機」、「タダノ」、「加藤製作所」について、それぞれの特徴をご紹介します。各メーカーのラインナップには様々な機種があり、現場のニーズに合ったモデルを選ぶことが大切です。
1.コベルコ建機
コベルコ建機は、油圧ショベルや移動式クレーンの開発、製造、販売、サービスを手掛ける重機メーカーです。同社のラフタークレーンは、都市部の狭い現場でもスムーズに移動できるよう、コンパクトなボディと高い走行性能が追求されています。
主要なモデルとして、最大定格総荷重4.9tの「リンクス130」や、25tの吊り上げ能力を持つ「RK250」などがあります。RK250は最大30mを超えるブーム長を誇り、高所作業にも対応可能です。
コベルコ建機の主なラフタークレーンを、以下の表にまとめました。
| 製品名 | 型式 | 最大定格総荷重 | ブーム長さ |
| リンクス130 | RK130M-2 | 4.9t×5.0m | 5.5~24.0m |
| RK130-2 | 13t×1.5m | ||
| RK250 | RK250-10 | 25t×3.5m | 9.35~30.5m |
| パンサー700 | RK700-3 | 70t×2.1m | 9.8~44.0m |
(引用元:ホイールクレーン|製品情報|コベルコ建機株式会社)
2.タダノ
タダノは、建設用クレーンや高所作業車などを製造・販売するメーカーです。1955年に日本初の油圧式トラッククレーンを開発して以来、クレーンメーカーとして実績を重ねています。特にラフタークレーンは、小回りが利く特性から市街地などの狭い現場での活躍が多いです。
タダノのラフタークレーンには、様々な吊り上げ荷重のモデルがあります。例えば、小規模な現場で活躍する3t、5t、6tクラス、汎用性の高い16t、25tクラスなどが挙げられます。
特に25tクラスのラフタークレーンは国内で最も普及しており、タダノはフル電動の25tラフタークレーン「EVOLT eGR-250N」を開発するなど、環境に配慮した製品も提供しています。
タダノの主なラフタークレーンを、以下の表にまとめました。
| 製品名 | 型式 | 最大定格総荷重 | ブーム長さ |
| エボルト | eGR-250N | 25t×3.5m | 9.35~30.5m |
| クレヴォG5シリーズ | GR-160N | 16t×3.0m | 6.5~28.0m |
| GR-250N | 25t×3.5m | 9.35~30.5m | |
| クレヴォG4シリーズ | GR-130NL/N(2W) | 13t×1.5m | 5.3~23.8m |
| GR-130NL/N | 5.5~24.0m | ||
| GR-600N | 60t×1.8m | 10.3~41.2m | |
| GR-700N | 70t×2.1m | 9.8~44.0m | |
| GR-1000N | 100t×1.6m | 10.2~48.0m | |
| GR-1450EX ※構内専用機 |
GR-1450EX | 145t×2.5m | 13.1~61.0m |
(引用元:ラフテレーンクレーン | 株式会社タダノ – 建設用クレーン車)
3.加藤製作所
加藤製作所は、ラフタークレーンをはじめとする建設機械の製造・販売を手がける総合建機メーカーです。同社のラフタークレーンは、幅広い吊り上げ能力を持つモデルが特徴です。
例えば、最大定格総荷重50tのモデル(SL-500RfⅢなど)、60tのモデル(SL-600RfⅢなど)、75tのモデル(SL-750RfⅢなど)、そして80tのモデル(SL-850RfⅢなど)を展開しています。
また、高所作業に対応する長尺ブームを備えたモデルも充実しており、現場のニーズに応じた最適な機種を選べます。
加藤製作所の主なラフタークレーンを、以下の表にまとめました。
| 機種名 | 型式 | 最大定格総荷重 | ブーム長さ |
| MR-100LSP-V | KR-10H-LII(PJ) | 10t×2.5m | 5.5~23.5m |
| MR-130RfⅡ(H,X) | KRM-13H-F2 | 13t×1.7m | 5.3~24m |
| MR-200Rf(X) | KRM-20H-F | 20t×2.5m | 6.5~28.0m |
| MR-250Rf | KRM-25H-F | 25t×2.8m | 6.7~29.0m |
| SR-250RfⅡ | KR-25H-F2 | 25t×3.5m | 9.35~30.5m |
| MR-350RfⅡ | KRM-35H-F | 35t×2.6m | 7.5~32.5m |
| SL-500RfⅢ | KR-50H-F2 | 50t×3.0m | 10.1~40.0m |
| SL-600RfⅢ | KR-60H-F2 | 60t×1.8m | |
| SL-750RfⅢ | KR-80H-FM2 | 75t×2.3m | 10.0~45.0m |
| SL-850RfⅢ | KR-80H-F2 | 80t×2.2m |
(引用元:ラフテレーンクレーン従来機種一覧|加藤製作所)
ラフタークレーンの用途・活躍する場所

ラフタークレーンは、不整地や狭い場所でも自走で進入できる機動性を備えており、土木・建築・解体・基礎工事・建柱工事・荷役作業など幅広い現場で活躍します。
例えば山林では、伐採後の木材をアウトリガーで安定させた車体から吊り上げる作業に適しており、トラッククレーンでは入りにくい場所でも作業可能です。
また、港湾部でのコンテナ荷役や河川沿いでの施工、災害時の復旧作業など、多様な環境に対応できます。さらに、クレーン先端にジブを装着すれば作業範囲が拡大し、高層ビルの上階や奥まった場所への資材搬入も可能です。
コンパクトな車体と小回りの良さから、市街地の建築現場やインフラ工事、イベント設営、樹木伐採などでも利用されており、その汎用性の高さが強みとなっています。
ラフタークレーンに必要な免許・資格
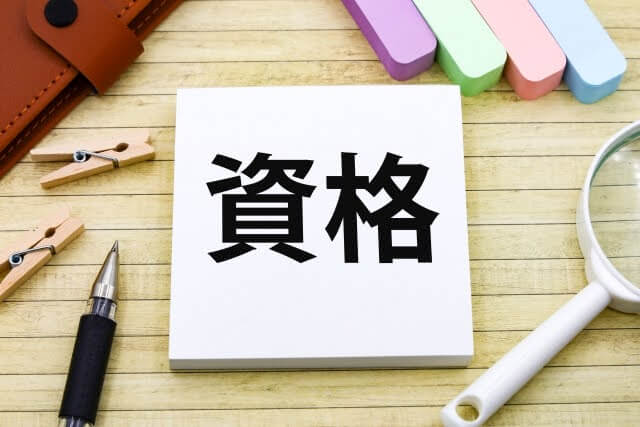
ラフタークレーンを運転するには、「大型特殊免許」と「移動式クレーン運転士免許」の2種類が必要です。これらの免許や資格の取得にかかる費用は、教習所や取得方法によって異なります。それぞれの免許について解説します。
1.大型特殊免許
大型特殊免許は、大型の特殊車両を公道で運転するために必要な資格です。ラフタークレーンは大型特殊自動車に該当するため、公道を走行する際にはこの免許が必須となります。取得難易度が高いと感じる方もいますが、決して取得が難しい資格ではなく、普通免許の有無に関わらず取得が可能です。
そのため、これからラフタークレーンの操縦を目指す方は、まずは大型特殊免許の取得から始めることをお勧めします。取得にかかる費用は教習所によって異なりますが、普通免許と比較して高額になる傾向があります。
大型特殊免許の取得条件
大型特殊免許を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
| 取得条件 | 詳細 |
| 年齢 | ・満18歳以上であること |
| 視力 | ・両眼で0.7以上 ・片眼で0.3以上 ・片眼が0.3未満の場合は、もう一方の眼の視野が150度以上あり、視力が0.7以上 |
| 色彩識別 | ・赤・青・黄色の区別ができること |
| 聴力 | ・10m離れた位置で90デシベルの警音器音が聞こえること ・補聴器による補助も可 |
| 身体 | ・運転に支障を及ぼす恐れのある四肢や体幹の障害がないこと ・補助装置を使って安全に運転できる場合は取得可能 |
| その他 | ・普通自動車免許は必須ではないが、教習所によっては保有が条件の場合もあり ・受講前に希望する教習所へ条件を確認することがおすすめ |
大型特殊免許の取得費用
大型特殊免許の取得にかかる費用は、取得方法や普通自動車免許の有無によって大きく変わります。
| 教習所 | 一発試験 | 合宿免許 |
| 普通免許あり:約10~15万円
普通免許なし:約17~22万円 |
初回費用:6,900円 (試験手数料2,800円、試験車使用料1,750円、免許交付料2,350円)※不合格の場合は、受験料と試験車使用料が毎回追加で必要 |
普通免許あり:約9~13万円
普通免許なし:約15~20万円 |
大型特殊免許の費用は、普通免許を持っていると技能教習時間が短縮されるため、費用を抑えやすい傾向にあります。
また、合宿免許の場合、最短4日程度で取得可能なプランもあり、滞在施設は相部屋から個室タイプまでさまざまなプランから選択可能です。
地域や教習所によっては夜間料金やキャンセル料が発生する場合もあるため、事前確認をしっかりとおこなうとよいでしょう。
大型特殊免許の合格率
大型特殊免許の合格率は、取得方法によって大きく変わります。警察庁のデータによれば、令和6年度の大型特殊免許の合格率は「85.3%」と高く、普通自動車免許の合格率「69.6%」を上回っています。
特に、指定教習所で学科と技能講習を受講し、卒業試験に合格した場合は、免許センターでの技能試験が免除されるため、ほぼ確実に取得できるのが特徴です。
一方で、免許試験場で直接受験する「一発試験」は難易度が高く、合格率はおよそ30%程度と低くなっています。一発試験では、運転技術や試験対策が十分でないと複数回の受験が必要になることも珍しくありません。そのため、短期間で確実に合格したい場合は、教習所を利用するルートが最も安全で効率的だといえるでしょう。
(引用元:令和6年版 運転免許統計|警察庁交通局運転免許課)
2.移動式クレーン運転士
移動式クレーン運転士は、吊り上げ荷重が5トン以上の大型移動式クレーンを操作するために必要な国家資格です。この資格の取得には、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があり、難易度の高い試験として知られています。試験に合格することで、クレーン作業を安全におこなうための専門知識と技術が証明されます。
また、資格取得にかかる費用は、講習機関や取得方法によって異なりますが、企業によっては資格取得支援制度を設けている場合もあります。
移動式クレーン運転士の取得条件
移動式クレーン運転士免許は、特別な学歴や職歴がなくても受験できます。年齢に関しても制限はないため、誰でも試験を受けられます。しかし、もし18歳未満で試験に合格した場合は、実際の免許交付は18歳の誕生日を迎えるまで保留されます。
そのため、高校在学中に合格しても、すぐに業務で運転できるわけではありません。
その他の条件は大型特殊免許と同様に、以下の条件を満たす必要があります。
| 取得条件 | 詳細 |
| 視力 | ・両眼で0.7以上 ・片眼で0.3以上 ・片眼が0.3未満の場合は、もう一方の眼の視野が150度以上あり、視力が0.7以上 |
| 色彩識別 | ・赤・青・黄色の区別ができること |
| 聴力 | ・10m離れた位置で90デシベルの警音器音が聞こえること ・補聴器による補助も可 |
| 身体 | ・運転に支障を及ぼす恐れのある四肢や体幹の障害がないこと ・補助装置を使って安全に運転できる場合は取得可能 |
移動式クレーン運転士の取得費用
移動式クレーン運転士の免許を取得する場合、教習所での受講費用と試験費用を合わせると、おおよそ13万円から16万円程度が目安となります。教習所での費用には、座学や実技講習の受講料が含まれており、受講者の経験や免許の有無によって費用は変動します。
加えて、学科試験の受験料は8,800円、実技試験の受験料は14,000円が別途かかります。教習所によっては、合宿形式で受講できるプランや分割払いが可能な場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。
移動式クレーン運転士の合格率
移動式クレーン運転士免許の試験は、学科と実技の両方で評価されます。令和6年の統計によると、学科試験の合格率は61.9%、実技試験も同様に64.7%となっています。つまり、受験者の半数以上がそれぞれの試験に合格している計算です。
ただし、学科と実技の両方を合格する割合は全体の約40%から50%程度にとどまるため、単独での合格よりも両方をクリアすることが重要です。
特に実技試験は操作の正確さや安全確認が求められるため、事前の練習や教習所での講習受講が合格率を高めるポイントとなります。教習所での実技教習を修了すれば、試験免除の規定を活用することも可能で、計画的に取得を目指すことが合格への近道です。
(引用元:統計 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会)
3.入社後の取得も可能な場合も
ラフタークレーンのオペレーターとして働く際、事前に資格が必要だと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、多くの企業では入社後の資格取得を認めており、未経験からでも安心してチャレンジできる環境が整っています。
会社によっては、大型特殊免許や移動式クレーン運転士免許などの取得にかかる費用を全額負担するケースや、資格取得後に手当が支給される場合もあります。このような資格取得支援制度を活用することで、働きながらスキルアップを目指し、キャリアを築いていくことが可能です。
ラフタークレーンと他クレーンとの違い

ラフタークレーンと他のクレーンには、それぞれ異なる特徴と用途があります。ラフタークレーン以外のクレーンについて紹介します。
1.トラッククレーン
トラッククレーンは、トラックをベースにクレーン装置が搭載された移動式クレーンです。公道を走行することに適しており、比較的コンパクトな車両から大型の車両まで、幅広いラインナップがあります。
運転席とクレーン操作席が分かれているタイプと、運転席で走行とクレーン操作の両方ができるタイプがあります。公道を走行するには、車両の大きさによって中型免許または大型免許が必要です。
また、クレーンを操作するためには、別途移動式クレーン運転士免許が求められます。
2.オールテレーンクレーン
オールテレーンクレーンは、「All Terrain(すべての地形)」という名の通り、舗装された道路だけでなく、整備されていない不整地でも走行できる移動式クレーンです。高速走行も可能なため、現場間の移動にも適しています。
大型の車両が多く、最大で700tもの吊り上げ能力を持つモデルも存在し、大規模な工事現場で活躍します。
ラフタークレーンが走行とクレーン操作を一つの運転席でおこなうのに対し、オールテレーンクレーンは走行用とクレーン操作用にそれぞれの運転席があることが特徴です。また、多軸方式が採用されており、非常に優れた安定性を持っています。
3.クローラークレーン
クローラークレーンは、クローラー(キャタピラ)を装着した台車にクレーン装置を備えた移動式クレーンです。タイヤ式クレーンに比べ地盤の影響を受けにくく、悪路や凹凸のある場所でも安定した走行と作業が可能です。接地面積が広いため接地圧が低く、荷重が均一に分散されることで、特に不整地や軟弱地盤での作業や重量物の吊り上げに適しています。
現場内での自走は可能ですが、公道での走行はできないため、運搬にはトレーラーが必要です。また、狭い場所での小回りが利きにくく、設置場所が限定されるデメリットもあります。
4.鉄道クレーン
鉄道クレーンは、線路の交換や橋梁の架け替えといった鉄道工事に特化した特殊なクレーンです。線路上を移動し、特に架線下のような狭いスペースでの作業に適しており、水平に物を吊り上げる能力に優れています。公道を走行するラフタークレーンとは異なり、鉄道クレーンは線路上でのみ運用される点が大きな特徴です。
5.浮きクレーン
浮きクレーンは、箱型の台船にクレーンが設置された移動式クレーンで、フローティングクレーンとも呼ばれています。陸上での作業に適したラフタークレーンとは異なり、海上や港湾での作業に特化している点が特徴です。これにより、水上での重作業を効率的におこなえます。
6.クレーン機能付きのドラグ・ショベル
クレーン機能付きドラグ・ショベルは、油圧ショベルにクレーンとしての機能を追加した移動式クレーンです。油圧シリンダーや油圧モーターによって操作され、クレーンモードとショベルモードを切り替えられる点が最大の特徴です。
そのため、一台で移動式クレーンと油圧ショベルの機能を兼ね備えており、多様な現場で柔軟な作業を可能にします。
ラフタークレーンについてよくある質問
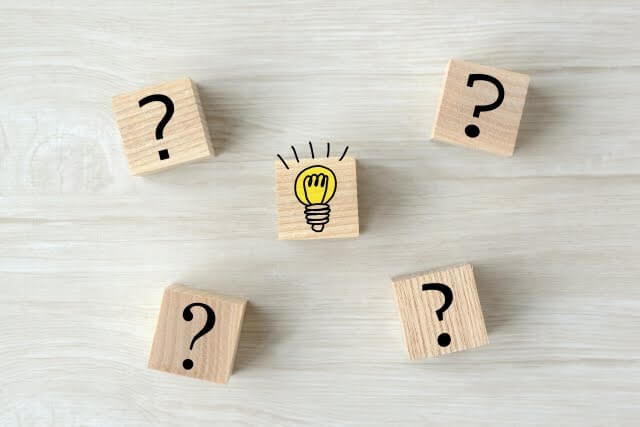
ラフタークレーンについて、よくある質問をまとめました。
ラフタークレーンとトラッククレーンの主な違いは?
ラフタークレーンとトラッククレーンの最も大きな違いは、運転席の構造と走行性能です。ラフタークレーンは一つの運転席で走行とクレーンの操作の両方が可能であり、不整地や狭い場所での走行性に優れています。
これに対し、トラッククレーンは基本的に走行用とクレーン操作用で別々の運転席を持つことが多く、公道走行に特化した設計です。これにより、ラフタークレーンは現場での機動性が高く、作業効率が向上します。
ラフタークレーンの吊り上げ能力はどのくらい?
ラフタークレーンの吊り上げ能力は、機種によって大きく異なります。小型のものでは4.9トンから、汎用性の高いものでは20トンから70トン、さらに大型のものでは80トン以上の吊り上げ能力を持つモデルもあります。
現場のニーズや吊り上げる荷物の重さに応じて、最適な能力のラフタークレーンを選択することが重要です。
ラフタークレーンのブームとジブの違いは?
ラフタークレーンにおけるブームとジブは、どちらも荷物を吊り上げるアーム部分を指しますが、呼び方や役割に違いがあります。
正式な名称は「ジブ」が用いられ、これはクレーン本体から斜め前方に伸びる腕のような部分を意味します。
一方、現場ではジブのことを「ブーム」や単に「アーム」と呼ぶこともあり、使用される呼称は会社や現場によって異なる場合があります。
一般的には、旋回台に取り付く主要なアーム部分をブーム(主ジブ)、その先端や補助的なアームを補助ジブやジブと呼んで区別することが多いです。
メーカーの仕様書でも、ブームとジブを分けて長さや角度を明記していることがあります。このように、ブームは作業の基幹となる主アーム、ジブは作業範囲を補助的に拡張するアームとして理解すると分かりやすく、現場で混同しやすい用語の違いも整理できます。
ラフタークレーンの免許試験の内容は?
ラフタークレーンを操作する「移動式クレーン運転士」の免許試験は、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があります。
学科試験では、移動式クレーン全般の知識に加え、原動機や電気に関する基礎知識、関連法令、さらにクレーン運転に必要な力学の理解が問われます。
具体的には、これらの分野から選択式で出題され、総合的な理解が求められます。
一方、実技試験では、ラフタークレーンを安全かつ正確に操作できる能力が試されます。具体的には、クレーンの運転操作に加え、作業現場で必要な合図の正確な実施が評価対象です。
試験は時間が区切られておこなわれ、学科試験は通常150分、科目免除者は120分で実施されます。実技試験は午前・午後に分かれ、受験者ごとに指定された時間に受験します。ラフタークレーン免許を取得するには、理論と操作の両方で確実な知識と技能を身につけていることが重要です。
まとめ
この記事では、ラフタークレーンとトラッククレーンの主な違いや、それぞれの特徴、必要となる免許について解説しました。
主要メーカーにはタダノ、加藤製作所、コベルコ建機があり、それぞれ多様なモデルを展開しています。現場環境や作業内容に応じて最適なクレーンを選ぶことで、作業効率と安全性を両立できます。
-
- ラフタークレーンは、不整地や狭い場所でも高い走行性能を発揮し、一つの運転席で走行とクレーン操作が可能
- ラフタークレーンは、小規模な工事現場や市街地での作業で活躍する
- ラフタークレーンとトラッククレーンの最も大きな違いは、運転席の構造と走行性能
- ラフタークレーンの免許には公道を走るのに必要な「大型特殊免許」と、クレーンを操作するのに必要な「移動式クレーン運転士」の2つがある






