【完全版】トラックのタイヤ交換方法|費用・相場・注意点

トラックのタイヤ交換は、安全な運行に欠かせない重要なメンテナンスです。タイヤには様々な種類があり、交換方法もJIS規格とISO規格で異なり、交換費用もサイズや依頼先によって変動します。
本記事では、タイヤの種類それぞれの交換方法や費用相場、交換時期、交換時の注意点まで詳しい情報を解説します。
目次
トラックのタイヤの種類

トラックのタイヤを交換する際には、まず自分の車両に適したタイヤの種類を正しく理解しておくことが大切です。タイヤの構造や特性を把握しておくことで、交換時の選択ミスを防ぎ、安全性や走行性能の向上にもつながります。
トラックのタイヤは、その内部構造からチューブタイヤとチューブレスタイヤに大別されます。近年ではチューブレスタイヤが主流です。また、タイヤの骨組みであるカーカスコードの配置によって、バイアスタイヤとラジアルタイヤに分けられます。
カーカスコードとは、タイヤの内部に組み込まれているコード層のことで、タイヤの強度や形状を保つ役割を担っています。
バイアスタイヤは、このカーカスコードを斜め方向に重ねて構成されており、ラジアルタイヤはカーカスコードを放射状に配置し、その上をベルトで補強した構造です。ラジアルタイヤは、優れた操縦性や走行安定性、耐摩耗性などのメリットがあり、多くのトラックで採用されています。
1.JIS規格・ISO規格
トラックのタイヤホイールには、JIS規格とISO規格の2種類が存在します。JIS規格は主に日本国内で採用されてきた規格ですが、近年製造される大型トラックでは国際的に広く普及しているISO規格の採用が増加傾向です。
それぞれの規格によって、ホイールの形状やボルトの数、ナットの締め付け方法などが異なります。そのため、タイヤ交換時には車両がどちらの規格に対応しているか必ず確認しましょう。万が一規格に合わない方法で作業をすると、事故につながる危険性があります。
2.トレッドパターン
トレッドパターンは、タイヤのゴムが路面に接する部分に刻まれた溝のデザインです。トレッドパターンによって、トラックの走行性能、特にグリップ力、排水性、そしてノイズに大きく影響を与えます。トラックの種類や主な用途に応じて、最も適したトレッドパターンを選ぶことが、安全で効率的な運行となります。
トレッドパターンの主な4つのカテゴリを紹介します。
リブ型
リブ型のトレッドパターンとは、タイヤの周囲方向に沿って縦に連続した溝が刻まれているのが特徴です。この構造により、走行中の直進安定性や操縦性が高まり、高速道路や舗装路といった良好な路面での運転に適しています。
また、タイヤが路面を転がる際の抵抗が小さく、燃費性能の向上にもつながります。
さらに、排水性にも優れており、雨天時の路面でも安定したグリップを保つことが可能です。リブ型は、横滑りが起きにくく、車両のふらつきを抑える効果もあるため、安全性の面でもメリットがあります。タイヤ走行時のノイズも抑えられており、静かで快適なドライブ環境を実現可能です。
これらの理由から、リブ型は乗用車はもちろん、小型トラックから大型トラック・バスに至るまで幅広く使用されています。
ラグ型
ラグ型のトレッドパターンとは、タイヤの回転方向に対してほぼ直角に溝が入っている構造が特徴です。この横方向の深い溝により、路面をしっかりとつかむ力が強く、特に駆動力や制動力、牽引力に優れています。未舗装路やぬかるんだ道など、悪路での走行性能が高いため、建設現場や農地、林道などで活躍するトラックや作業車両によく採用されています。
また、岩場や砂利道といった過酷な環境でもタイヤが傷つきにくい構造となっており、耐カット性の高さもラグ型の大きな特徴です。一方で、舗装路においては振動や騒音が大きくなりやすいため、主にオフロード用途に向いているタイヤといえるでしょう。
ラグ型はその高いグリップ力と耐久性から、中・大型トラックや建設機械、農業用車両など幅広い業種の車両で使用されています。
リブラグ型
リブラグ型のトレッドパターンとは、リブ型とラグ型の特性を組み合わせた構造で、タイヤの周方向と横方向の両方に溝が刻まれています。リブ部分は操縦時の安定性を高め、直進性や横滑りの抑制に貢献する構造です。
一方、ラグ部分は駆動力や制動力の向上に寄与し、滑りやすい路面や悪路でもしっかりとしたグリップ力を発揮します。
こうした特徴から、リブラグ型は舗装路と未舗装路のどちらにも対応できる汎用性の高いパターンといえます。都市部から郊外、あるいは建設現場まで幅広い走行環境に対応できるため、中・大型トラックやバス、建設車両、産業車両などさまざまな用途で使用されています。どちらか一方のパターンでは補いきれない性能をバランスよく持ち合わせており、走行安定性と路面への食いつきの両立を求める車両に最適な選択肢です。
ブロック型
ブロック型のトレッドパターンとは、タイヤ表面に独立したブロック状の突起が並んでいるのが特徴です。この形状により、雪道や泥濘地のような悪路での走行性能が非常に優れており、高い駆動力と制動力を発揮します。各ブロックが路面をしっかりと掴むため、滑りやすい環境でも安定した走行が可能です。特に冬季のスタッドレスタイヤやスノータイヤには、このブロック型が多く採用されており、積雪路や凍結した路面での安全運転をサポートします。
また、オフロード用のタイヤにも用いられ、林道や未舗装路でのトラクション確保にも効果的です。ただし、舗装路での走行時はブロック同士の隙間によって走行音が大きくなりやすく、燃費にも悪影響を与えることがあります。ブロック型は、悪条件の路面での性能を重視する車両にとって欠かせないトレッドパターンと言えるでしょう。
【JIS規格・ISO規格】トラックのタイヤ交換方法

ここでは、JIS規格とISO規格それぞれのトラックのタイヤ交換方法について詳しく解説します。工具や具体的な手順・流れを理解し、安全にタイヤ交換をおこないましょう。
【JIS規格】交換方法
この章では、JIS規格タイヤの交換方法、スペアタイヤを含むタイヤ交換に必要な工具と、交換作業の詳しい手順を解説します。安全かつ正確な作業をおこなうため、手順をしっかりと理解して進めましょう。
【JIS規格】必要な工具
JIS規格のトラックタイヤ交換では、下記の専用工具などが必要です。
| 専用工具 | 用途 |
| ホイールナットレンチ | ホイールナットの脱着 |
| 鉄パイプ | レンチに装着して使用することで、より大きな力をかけてナットを緩めたり締めたりできる |
| ストッパー | タイヤ止めとして使用し、車両が動かないように固定する |
| ジャッキ | 車両を持ち上げるため |
| 軍手 | 作業中に手を保護する |
ジャッキには、軽量で手頃な「パンタグラフジャッキ」と、安定性が高く作業が楽な「油圧ジャッキ」があります。
パンタグラフは、収納性に優れますが横からの力に弱く、油圧は重いものの安定感があるという特徴があります。迷ったら専門店で相談しましょう。
これらの工具を事前に準備することで、スムーズかつ安全にJIS規格のタイヤ交換を進められます。
【JIS規格】交換手順・流れ
JIS規格タイヤ交換の流れは、以下のとおりです。
|
1.まず車両を安全な場所に停車させ、輪止めで固定します。 2.ジャッキアップポイントにジャッキをかけ、タイヤが地面から離れるまで車両を持ち上げます。後輪がダブルタイヤの場合は、外側のタイヤを外すと内側にもナットがあるため、インナーナットを緩めて外します。 3.古いタイヤを取り外し、新しいタイヤを取り付けたら、インナーナットとアウターナットをそれぞれ仮締めします。 4.ジャッキを下ろし、車両の重さがタイヤにかかった状態で、トルクレンチを使用して規定トルクで本締めして完了です。 |
JIS規格では、右側のタイヤは右ねじ、左側のタイヤは左ねじとなるため、ナットを緩める方向が異なるので、念入りに確認しましょう。
【ISO規格】交換方法
ISO規格のトラックタイヤ交換は、JIS規格とは異なる手順でおこないます。安全かつ確実に作業を進めるためには、適切な工具の準備と正確な手順の理解が不可欠です。ISO規格のタイヤ交換に使う工具や具体的な手順、そして作業時の注意点について説明します。
【ISO規格】必要な工具
ISO規格のタイヤ交換には、JIS規格とほぼ同様の工具ですが、ホイールナットのサイズが異なる場合があるため、適切なサイズのソケットレンチを準備することが大切です。
また、ISO規格のホイールはセンター出しが欠かせないため、ホイールセッティングツールなどがあると便利に作業ができます。
ホイールセッティングツールは、自動車や大型車のホイール脱着時に位置決めを補助する専用工具です。重いホイールの取り付けを安全かつ効率的におこなうために役立ちます。
これらの工具を事前に準備しておくことで、スムーズかつ安全に作業を進められます。
【ISO規格】交換手順・流れ
JIS規格タイヤ交換の流れは、以下のとおりです。
|
1.トラックを平坦で安全な場所に停車させ、パーキングブレーキをかけます。反対側のタイヤに輪止めをして車両の動きを防ぎます。 2.スペアタイヤを取り出しやすいように準備し、ホイールナットをレンチで90度ほど緩めておきます(完全には外しません)。 3.指定のポイントにジャッキをかけ、タイヤが地面から1〜2cm浮くまで持ち上げます。 4.を外して古いタイヤを取り外し、新しいタイヤを装着。ナットは対角線順に手で仮締めし、レンチで軽く固定します。 5.車体を下ろし、ナットを対角線順で本締め。最後に空気圧を調整し、全体を確認して完了です。 |
トラックのタイヤ交換にかかる費用・相場
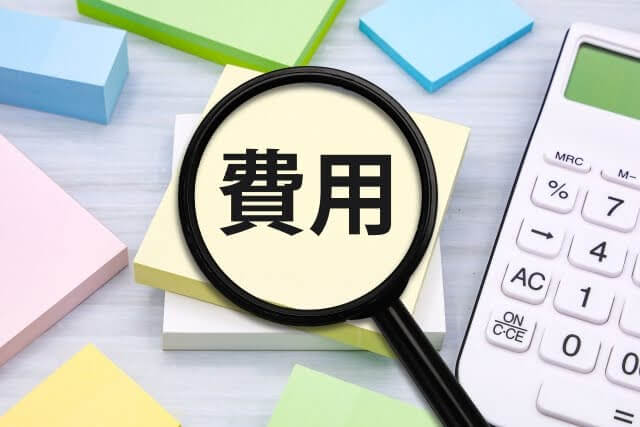
トラックのタイヤ交換にかかる費用は、主にタイヤ本体の料金と交換にかかる工賃の合計で決まります。交換工賃も、トラックのサイズによって変動します。ホイールバランス調整や廃タイヤ処理費用が別途かかる場合もあるため、事前に確認をしておきましょう。
タイヤ本体価格(料金)
トラックのタイヤ本体価格は、種類やサイズ、メーカー、性能で変動します。
小型・中型トラックで使用されることが多い15~17.5インチクラスのタイヤは、1本あたり10,000円から25,000円程度が目安です。サイズが大きくなるほど価格も高くなる傾向があります。
小型・中型トラックは主に4輪なので、全交換には4本分の費用がかかります。費用を抑えたい場合は、車両に搭載されているスペアタイヤを利用することも可能ですが、緊急時の備えがなくなる点に注意が必要です。
交換工賃相場
トラックのタイヤ交換にかかる工賃は、タイヤの着脱作業に加え、組み換え・組み込み、そして取り外した古いタイヤの処理費用などが含まれます。これらの工賃は、トラックのサイズやタイヤのホイール径によって異なります。
一般的に、2トントラックでは1本あたり2,500円程度、3トントラックでは2,750円程度、4トントラックでは3,000円程度が目安です。全タイヤを交換する場合は、交換する本数分の工賃がかかります。ただし、これらの金額はあくまで参考であり、依頼する専門業者によって費用は変動します。
また、スペアタイヤを持ち込んで交換を依頼する場合は、タイヤ本体の料金はかかりませんが、交換工賃は発生します。
タイヤ交換時期の目安
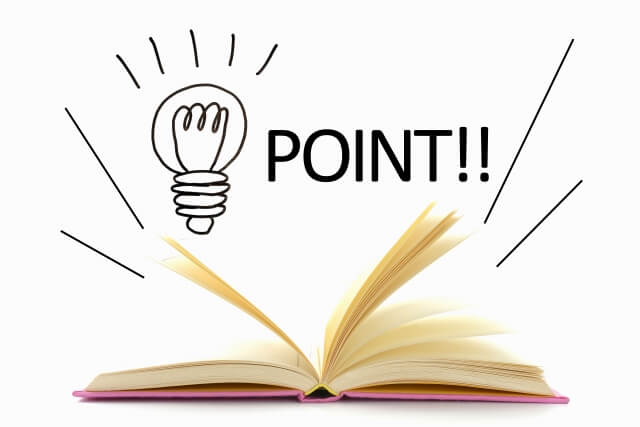
トラックのタイヤ交換時期は、一般的に、走行距離では3万kmから5万km、使用年数では3年から5年程度が交換時期の目安とされています。
ただし、運転方法や積載量、走行する道路環境によって摩耗の進行は異なります。特にタイヤの「スリップサイン」や「ひび割れ」が見られる際には早めに交換をおすすめします。
スリップサイン

スリップサインとは、タイヤの残り溝が限界に近づいたことを知らせる重要な目印です。タイヤの側面には三角マーク(△)が刻まれており、その延長線上の溝の中に、通常より盛り上がった部分が存在します。これがスリップサインであり、残り溝が1.6mm以下になると現れるように設計されています。
スリップサインが露出しているタイヤは、排水性が大きく低下しており、特に雨天時にはスリップやハイドロプレーニングのリスクが高まります。
また、制動距離が長くなる、グリップ力が低下するなど、安全性が著しく損なわれるため、早急な交換が必要です。車検にも通らず、法律上も公道走行が認められていません。
なお、タイヤは均等に摩耗するとは限らないため、4輪すべてのスリップサインの有無を複数箇所で確認することが重要です。
ひび割れ

タイヤのひび割れとは、タイヤ表面にできる細かな亀裂のことで、主にゴムの経年劣化によって発生します。トレッド面(接地面)やサイドウォール(側面)、ショルダー部(側面と接地面の境目)に現れやすく、特に長期間使用しているタイヤや紫外線・熱・空気圧の管理不良によって進行しやすくなります。
浅いひびであればすぐに交換の必要はない場合もありますが、ひび割れが深くなり内部のコード層にまで達すると、パンクやバーストを引き起こす危険があります。
そのため、ひび割れを見つけた際は、大きさや深さをチェックし、進行の兆候がある場合は早めに専門業者で点検を受けることが大切です。安全走行のためにも、溝の深さだけでなく、ひび割れの有無も定期的に確認しましょう。
トラックのタイヤ交換時の注意点
タイヤ交換を安全かつスムーズにおこなうには、下記の4つの注意点があります。
| 1.ナットやトルクの締まり具合 2.交換作業後は必ず試運転をする 3.作業前の安全確認と準備 4.逆ネジに注意する |
それぞれの注意点を解説します。
1.ナットやトルクの締まり具合
タイヤ交換が完了したら、確実にナットが締め付けられているか、また、適正なトルクで締め付けられているかの確認をします。これにより、走行中のホイール脱落といった重大な事故を防げます。
また、タイヤ交換後は、走行することでホイールとハブが徐々に馴染み、ナットが緩んでしまうことがあります。そのため、交換後100km程度走行したタイミングで「増し締め」をすることが非常に重要です。この作業によって、ホイールの脱落やナットの緩みを防ぎ、走行中の安全性を高められます。
ナットを締める順番にも注意が必要です。ナットを均等に締め付けるために、「対角線パターン」での締め付けをおこないます。たとえば、5穴のホイールであれば「1→3→5→2→4」、4穴の場合は「1→3→4→2」のように、対角の位置を順番に締めていくのが基本です。増し締めの際は、必ずトルクレンチを使って適正なトルクで締め付けるようにしましょう。
こうした丁寧な増し締め作業をおこなうことで、トラックのタイヤ脱落事故を未然に防げます。
2.交換作業後は必ず試運転をする
タイヤ交換作業が完了したら、必ず試運転をしてください。これは、交換したタイヤやホイールが車両に適切に取り付けられているか、異常がないかを確認するための重要な工程です。
試運転中は、異音や振動がないか、走行に違和感がないかなどを慎重に確認しましょう。万が一、異常が見られる場合は、速やかに車両を停車させ、ナットの緩みなどを再度チェックします。不安があるようなら、専門業者に点検を依頼することをおすすめします。
3.作業前の安全確認と準備
タイヤ交換作業を安全におこなうためには、事前の確認と準備は必須です。まず、作業場所は平坦で安定した場所を選び、車両が動かないように輪止めをしっかりと設置しましょう。
次に、交換に必要な工具が全て揃っているか確認し、損傷がないか事前に点検します。特に、ジャッキはトラックの重量に耐えられるものを選び、トルクレンチは正確なトルク値に設定できるか確認が必要です。
また、取り付け面にサビや泥、異物がついていると、ホイールが均等に取り付けられず、振動や緩みの原因になります。作業前にはワイヤーブラシ等で取り付け面やボルト穴をきれいに掃除し、傷や変形がないかを確認しましょう
4.逆ネジに注意する
トラックのタイヤ交換時は、「逆ネジ」の存在に十分注意しましょう。逆ネジとは、通常のネジとは逆方向に締め付ける構造を持ったネジのことです。一般的なネジが「時計回り」で締めるのに対し、逆ネジは「反時計回り」で締める仕組みになっています。
トラックでは、走行中にホイールナットが緩んでしまうのを防ぐため、特に後輪の左側に逆ネジが使用されるケースが多く見られます。
逆ネジに気づかず通常の方向に回してしまうと、ボルトやナットを破損する恐れがあるため非常に危険です。逆ネジの見分け方としては、ナットに「L」や「LH(Left Hand)」といった刻印があるほか、ナットの色や形状が異なっている場合もあります。
トラックの逆ネジの使用箇所は、車種やメーカーによって異なるためタイヤ交換をする前は、必ず取扱説明書を確認するか整備の専門業者に相談しましょう。安全にタイヤ交換のためには、トラック特有の仕様を理解しておくことが大切です。
トラックのタイヤ交換時期を伸ばす方法

トラックのタイヤ交換は、装着タイヤが多いだけに経済的負担も大きくなってしまうため、タイヤ交換時期を少しでも伸ばしたいと考える方は少なくありません。運転方法やメンテナンスで、トラックのタイヤ交換時期を伸ばせるため、そのポイントを紹介します。
運転方法
トラック運転中に、急加速・急ブレーキ・急ハンドルなどの急の付く操作を控えることで、タイヤへの負担が軽減されます。また、スピードを抑えた運行をおこなえば熱によるタイヤの劣化速度も抑えられるので、余裕のある運転を心がけることが重要です。
メンテナンス
トラックのタイヤ交換時期を伸ばすためには、下記のメンテナンスが大切です。
| 1.タイヤの空気圧を保つ 2.タイヤローテーションをおこなう 3.タイヤの保管方法に気をつける |
それぞれのメンテナンス方法について紹介します。
1.タイヤの空気圧を保つ
トラックのタイヤ寿命を延ばすうえで、空気圧の管理は欠かせません。タイヤの空気は自然に抜けていくため、放置すると適正値を下回ることがあります。空気圧が不足しているとタイヤが変形し、両端に過度な負荷がかかることで偏摩耗が起こり、寿命が縮まります。
逆に空気圧が高すぎると中央だけが摩耗するセンター摩耗の原因となります。どちらもタイヤの性能を十分に発揮できず、燃費や操縦性にも悪影響です。
指定の空気圧は車両のドア付近などに表示されているので、月に1回は点検し、適正値を保つようにしましょう。空気圧の点検はガソリンスタンドや整備工場などでも手軽におこなえます。タイヤを長持ちさせるためにも、日常点検に空気圧チェックを取り入れることが大切です。
2.タイヤローテーションする
トラックのタイヤは、装着される位置によって負担や摩耗の進み方が異なります。特に前輪と後輪、駆動輪と非駆動輪では摩耗の度合いに差が出やすく、偏摩耗をそのままにしておくとタイヤの寿命を縮めてしまいます。
そこで効果的なのが、タイヤの装着位置を定期的に入れ替える「タイヤローテーション」です。走行距離が5,000km程度を目安におこなうと、摩耗のバランスが整い、タイヤ全体を長く使えます。
ローテーションの方法は駆動方式によって異なるため、迷った場合は専門業者に依頼するのが安心です。また、ローテーションと併せてアライメント調整もおこなえば、より効率的に寿命を延ばせます。タイヤ交換の頻度を抑えるためにも、ローテーションは定期的に実施しましょう。
3.タイヤの保管方法に気をつける
トラックのタイヤを長持ちさせるには、保管方法にも気を配る必要があります。タイヤはゴム製のため、直射日光や雨、湿気、熱などの影響で劣化が進みやすいです。特に、使用しない期間に屋外で保管してしまうと、ひび割れや変形が生じる恐れがあります。
保管する際は、直射日光を避けた涼しく風通しの良い場所を選び、可能であればタイヤカバーをかけましょう。また、タイヤの空気をそのままにしておくと形が崩れる原因になるため、空気圧は半分程度に減らしておくのが理想的です。
さらに、ホイール付きのタイヤは横置きで、ホイールなしのタイヤは縦置きで保管すると形状変化を防ぎやすくなります。保管場所の確保が難しい場合は、タイヤ預かりサービスの利用も検討することをおすすめします。
タイヤ交換に関するよくある質問
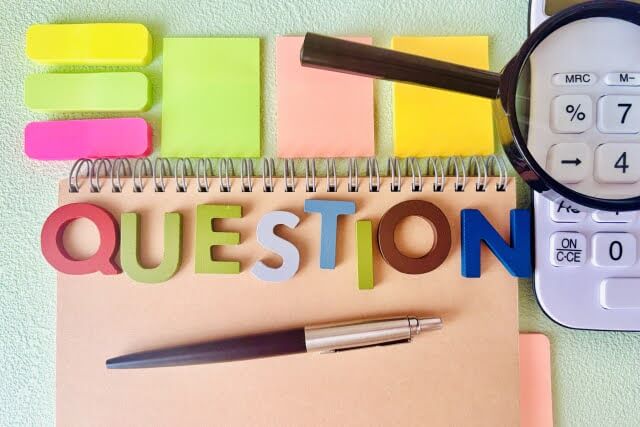
トラックのタイヤ交換に関する質問をまとめました。
タイヤ交換が必要な理由は?
トラックのタイヤ交換は、安全な運行を守るために重要です。タイヤは走行により摩耗し、ゴムが硬化すると路面とのグリップ力が低下します。グリップ力が弱まると、特に雨天時の滑りやすさが増し、事故のリスクが高まります。
また、タイヤのひび割れや摩耗が進むと、走行中にパンクやバーストを起こす可能性があり、これも重大事故につながる可能性があり危険です。
さらに、摩耗したタイヤは衝撃吸収力が弱まり振動が増えるため、乗り心地が悪化し燃費も低下します。
こうしたトラブルを防ぐためにも、定期的にタイヤの状態をチェックし、適切なタイミングで交換することが安全かつ快適な走行には欠かせません。
溝が残っているタイヤは、まだ使える?
タイヤに溝が残っている場合、走れないことはありません。しかし、経年劣化で強度が低下し、ひび割れなどが生じやすくなります。
擦り減りが激しい場合、いきなりタイヤが破裂するバーストのリスクが潜んでいます。タイヤがバーストしたトラックは、コントロールを失い衝突・追突事故に繋がりかねません。事故を防ぐために、タイヤの状態は定期的に確認しましょう。
摩耗タイヤは道路交通法違反の処罰対象になる?
国内で運行するトラックは、タイヤの溝の深さも国土交通省の定める保安基準の規制を受けます。そのため、タイヤ交換時期を過ぎたトラックは、車検を通過できません。
|
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示第619号) |
さらに、タイヤ交換時期を過ぎた状態でトラックを運行させた場合、整備不良の道路交通法として、下記の処分を受ける可能性があります。
| ・違反点数2点 ・罰金(普通車は9,000円、大型車は12,000円) |
タイヤ交換はどれくらいかかる?
大型トラックの場合、タイヤが大きく重量もあるため、時間が必要です。交換時間の目安としては、1本の交換に20~30分ほどかかります。特にリアのダブルタイヤは本数が多く、交換時間が長くなる傾向があります。
中型や小型トラックではタイヤが小さいため、交換時間はやや短くなりますが、それでも1本あたり15~25分はかかります。
業務に支障をきたさないためにも、余裕を持ったスケジュールで交換することが大切です。
まとめ
トラックのタイヤ交換は、安全な走行と事故防止のために欠かせないメンテナンスです。タイヤの種類や規格に応じた正しい交換方法を理解し、適切な時期に交換することが重要です。
また、交換費用や作業時間はタイヤのサイズや車種によって異なります。日頃からタイヤの溝やひび割れを点検し、異常があれば早めの交換を心がけましょう。適切なメンテナンスを続けることで、トラックの走行性能や燃費を維持し、長く安全に使用できます。
-
- トラックのタイヤの種類は、JIS規格・ISO規格、トレッドパターンがある
- 交換方法・費用は、タイヤの種類やサイズ、自分でおこなうか業者に依頼するかで異なる
- タイヤの交換時期を延ばすため、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどの運転方法を工夫したり、定期的にタイヤローテーションをおこなうなど定期メンテナンスを心がける






