【対処法】トラックドライバーの違反点数・免停期間|知っておくべき重要な情報
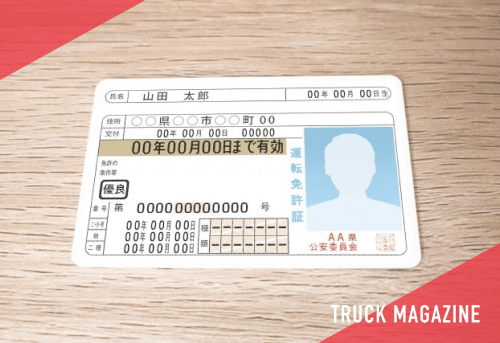
道路交通法の違反による点数や免停期間は、トラックドライバーにとって仕事に多大な悪影響を与える違反行為です。違反点数が一定数を超えると免停の対象になり、長期間の運転禁止を受ける可能性があります。
この記事では、トラックドライバーが違反点数や免停期間を正確に理解し、もし免停になった場合、どのような対処法があるのか解説します。
目次
免停とは?

免停とは、運転免許証が一時的に効力を停止される行政処分のことです。交通違反を繰り返したり、重大な違反行為をおこなったりした場合に、道路交通法に基づいて課せられます。具体的には、違反点数が一定基準を超過した場合や、飲酒運転などの特定の重大な違反があった場合に免停処分となります。
これにより、運転免許証が指定された期間使えなくなり、車の運転が一切できなくなります。免停処分は、運転者にとって移動の自由を奪われるだけでなく、職業上の影響や日常生活における制約を伴うため、重大な行政処分といえます。
免許の点数とは
交通違反をすると、違反内容に応じて点数が加算されます。軽い違反は数点、酒気帯び運転などの重大な違反では10点以上がつくこともあります。
この点数が一定期間に累積6点以上になると免許停止となり、前歴がある場合はさらに厳しく処分されます。
点数には有効期間があり、違反後1年間無事故無違反であればリセットされます。
また、2年以上無事故・無違反の状態で、3点以下の軽微な違反をした後、さらに3ヶ月間無事故無違反であれば、その3点の点数も計算から除外される特例もあります。
ただし、酒酔い運転やひき逃げなど重大違反の場合は、2年間点数が保持されるなど例外も設けられています。
【基準】免許停止にいたるまでの点数計算
免停や免許取消の基準は、違反点数だけでなく過去の処分歴(前歴)の有無によっても変わります。
初めての違反なら6点から免停になりますが、過去に免停や取消を受けたことがあると、より少ない点数でも免停や取消の対象となります。
| 3年間での違反回数 | 免許停止になる点数 |
| なし | 6点 |
| 1回 | 4点 |
| 2回以上 | 2点 |
【一覧表】一発免停となる違反行為と点数
一度の違反だけで免許停止処分となる、いわゆる「一発免停」に該当する行為があります。これらは特に悪質、または危険性が高いと判断される違反です。
下表にまとめたので、参考にしてください。
| 違反内容 | 点数 | 免停日数の目安 | 解説 |
| 酒気帯び運転 (呼気0.25mg/L以上) |
25点 | 免許取消対象 | ・一発で免停どころか取消。 ・職業運転手としては致命的。 |
| 酒気帯び運転 (呼気0.15〜0.25mg/L未満) |
13点 | 同上。軽度でも厳罰。 | |
| 無免許運転 | 25点 | ・他人の免許を借りて運転した場合も同様。 | |
| ひき逃げ(救護義務違反) | 35点 | ・刑事罰+行政処分。 ・業界復帰はほぼ不可能。 |
|
| 酒酔い運転 | 35点 | ・酩酊状態での運転。・ 最重罰クラス。 |
|
| 危険運転致傷(刑事事件) | 62点 | 実刑判決の可能性が高い。 | |
| 制限速度超過(30km以上オーバー) | 6点 | 30日免停 | 高速道路でのスピード違反が多い。 |
| 踏切不停止(事故伴う場合) | 6点 | トラックは車体が大きいため重大事故に直結する。 | |
| 携帯電話保持(事故伴う場合) | 6点 | 運転中に、通話や画面を注視してして事故を起こした場合。 | |
| 信号無視(重大事故につながる場合) | 9点 | 60日免停 | 赤信号を無視して事故に至ると高点数になる。 |
| 過労運転(居眠り含む)による事故 | 6〜13点 | 30〜90日免停 | ・トラック業界特有。・ ・労働時間管理不足で多発。 |
| 無謀運転(幅寄せ・急ブレーキなど危険行為) | 6点以上 | 30日免停〜取消 | ドライブレコーダー映像で摘発される例も増加。 |
例えば、酒気帯び運転では、呼気中のアルコール濃度に応じて13点または25点の点数が科され、即座に免許停止または取り消しとなります。
また、一般道で時速30キロ以上50キロ未満の速度超過は6点、時速50キロ以上では12点となり、いずれも一発免停の対象です。
このほか、無免許運転(25点)や、大型自動車の過積載(積載重量10割以上)なども6点の違反点数となり、一度の違反で運転資格を失う可能性があります。
その他の一発免停ではありませんが、減点となる違反行為もあわせてご確認ください。
| 違反内容 | 点数 | 解説 | |
| 無車検運行・無保険運行 | 無車検運行 | 6点 | 車検が切れたり強制保険である自賠責保険に未加入で運転した場合、無車検運行、無保険運行で違反点数対象となる。 |
| 無保険運行 | 6点 | ||
| 速度超過 | 20キロ未満 | 1点 | 走行する道路にはそれぞれ定められた速度があり、その速度を超えてしまった場合、違反となる。 |
| 20~25キロ未満 | 2点 | ||
| 25~30キロ未満 | 3点 | ||
| 駐停車禁止違反 | 駐停車禁止 | 2点 | 駐車禁止違反は、駐車も停車も禁止である「駐停車禁止」と、停車だけなら良い「駐車禁止」の2種類に大別される。 |
| 駐車禁止 | 3点 | ||
| 信号無視 | 2点 | 赤信号での走行はもちろん罰則の対象ですが、点滅信号の無視も違反の対象となる。 | |
| 整備不良 | 灯火周り不良 | 1点 | 灯火周りや制動装置の不備は違反点数対象となる。 |
| 制動装置不良 | 2点 | ||
| 携帯電話使用 | 3点 | 運転中に、通話や画面を注視してしまった状態などが違反の対象となる。 | |
免許取り消しとの違い
免許取り消しは、免許停止よりもはるかに重い行政処分であり、運転免許そのものの効力を失わせるものです。
免許取り消しのルールは、過去の行政処分歴と累積した違反点数によって厳格に定められています。例えば、前歴がない場合でも累積点数が15点に達すると免許取り消しとなります。
また、酒酔い運転(35点)やひき逃げ(35点)などの特定の違反行為は、一度犯しただけで免許取り消しの対象です。
処分を受けると、免許を再取得できない「欠格期間」が設けられ、この期間が満了しない限り、運転免許試験を受けることすらできません。トラックドライバーにとって、免許取り消しは事実上の失職を意味します。
免停の期間とは

免停では、違反点数と、過去の違反歴により、免停の期間が異なります。
本章では、それぞれ解説します。
違反点数に伴う免停期間
過去に違反歴がない場合の点数ごとの免停期間は、次のとおりです。
| 違反点数 | 免停期間 |
| 6~8点 | 30日間 |
| 9~11点 | 60日間 |
| 12~14点 | 90日間 |
(参照元:警視庁ホームページ)
違反点数が高くなるほど免停期間は長くなります。特に初めての違反であっても、一度に大きな違反をするとすぐに60日以上の免停となるケースもあるため注意が必要です。
違反点と前歴に伴う免停期間
過去に免停や取消を受けたことがある場合は、より少ない点数で長期間の免停や取消処分となります。
小さな違反でも積み重なると免停につながるため、日常的に安全運転を徹底してください。
過去に免停や取消を受けたことがある場合は、より少ない点数で長期間の免停や取消処分となります。
小さな違反でも積み重なると免停につながるため、日常的に安全運転を徹底してください。
| 違反点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 1 | |||||
| 2 | 90日間 | 120日間 | 150日間 | ||
| 3 | 120日間 | 150日間 | 180日間 | ||
| 4 | 60日侃 | 15日間 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | |
| 5 | 60日間 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | |
| 6 | 30日間 | 90日間 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
| 7 | 30日間 | 90日間 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
| 8 | 30日間 | 120日間 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
| 9 | 60日間 | 120日間 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
| 10-11 | 60日間 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
| 12-14 | 90日間 | 取消1年(3年年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
免停期間を短縮できる?免停後の講習とは?

免許停止の処分を受けても、一定の条件を満たせば「講習を受講することで免停期間を短縮」できる制度があります。
この制度を利用すると、トラックドライバーは、仕事復帰を早められます。ここでは、代表的な「違反者講習」と「停止処分者講習」を解説します。
【違反者講習】受講条件・メリット
違反者講習は、軽微な違反を繰り返し、累積6点になった方を対象とした免許停止処分にならないための講習です。
詳細を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 対象となる人 | 累積点数3点以下の違反者 |
| 講習時間 | 約3時間 |
| 費用 | 6,000〜7,000円 |
| メリット | 免停処分を回避できる |
過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。
「実車による安全運転講習」や「交通安全活動体験講習」など4つのコースがあります。コースによって事前予約が必要なものや1日で受講完了するものや2日間かけて受講するものがあります。
(参照元:警視庁ホームページ)
【停止処分者講習】種類・短縮日数
免停がすでに確定した場合でも「停止処分者講習」を受けることで免停期間を短縮できます。
講習の種類は、免停期間によって次のとおり分かれます。
| 講習の種類 | 受講対象 | 講習時間 | 短縮日数 |
| 短期講習 | 30日免停者 | 約1日(7時間) | 免停30日 → 免停1日に短縮 |
| 中期講習 | 60日免停者 | 約2日 | 最大30日短縮 |
| 長期講習 | 90日免停者 | 約3日 | 最大45日短縮 |
講習内容は、全ての講習で「運転適性検査の実施と指導」「自動車等による運転の適性診断と指導」「プロジェクターを使用した講義等」が実施されます。
(参照元:警視庁ホームページ)
トラックドライバーの免停が仕事に与える影響

業務の遂行が難しくなる
トラックドライバーにとって、免許停止は業務に不可欠な運転ができなくなるため、極めて深刻な事態となります。免停期間中はトラックの運転が一切できませんので、配送業務などの本来の業務に従事することはかないません。会社側の対応は就業規則などによって異なりますが、運転以外の業務(倉庫作業や事務作業など)へ一時的に配置転換されるケースがあります。
しかし、代替業務がない場合や、免停期間が長期にわたる場合は、休職を命じられたり、最悪のケースではクビにされる可能性も否定できません。
信用の低下
免停はドライバー本人だけでなく、勤務先の会社の信用にも関わります。
物流業界は荷主からの信頼関係で成り立っており、ドライバーが免停になることで「安全管理が不十分ではないか」と疑念を持たれるリスクがあります。
結果として契約の見直しや仕事の減少につながることもあります。
また、免停の記録は前歴として残るため、ドライバー自身が転職を希望した場合にも「安全面に不安がある人材」と評価されかねません。
とくに酒気帯び運転や過労運転など社会的に厳しく見られる違反は、再就職の妨げとなります。
免停はドライバー本人だけでなく、勤務先の会社の信用にも関わります。
物流業界は荷主からの信頼関係で成り立っており、ドライバーが免停になることで「安全管理が不十分ではないか」と疑念を持たれるリスクがあります。
結果として契約の見直しや仕事の減少につながることもあります。
また、免停の記録は前歴として残るため、ドライバー自身が転職を希望した場合にも「安全面に不安がある人材」と評価されかねません。
とくに酒気帯び運転や過労運転など社会的に厳しく見られる違反は、再就職の妨げとなります。
トラックドライバーが免停になった場合の対応策【個人・組織】
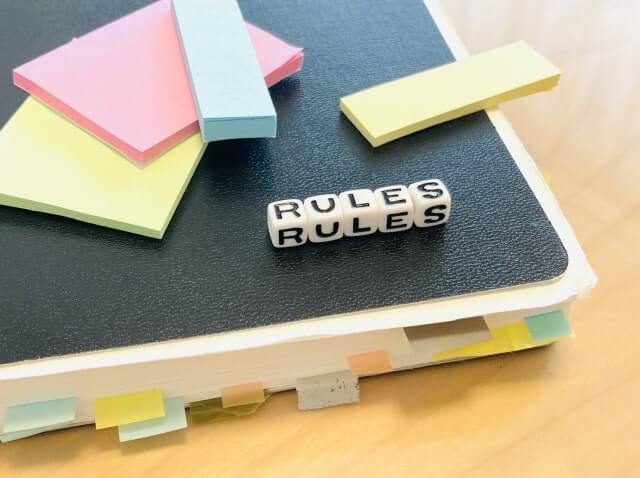
トラックドライバーにとって、免許停止は職業生命を揺るがす重大事態です。免停期間中は運転業務が一切できなくなるため、収入が途絶えるか、大幅に減少するリスクに直面します。
会社側も、ドライバーが一人欠けることで代替人員の確保や配送計画の再調整に追われ、事業運営に大きな支障が生じます。個人の問題だけでなく、所属する会社や取引先にも多大な迷惑をかけることになり、信頼関係の損失にもつながりかねません。
ここでは、ドライバー個人と会社、それぞれの立場から見た対応策を解説します。
1.ドライバー個人への対応策
万が一、免許停止処分を受けることになった場合、ドライバーがまず取るべき行動は、会社への迅速かつ正確な報告です。この報告を怠り、無断で運転を続けると無免許運転となり、発覚した際には懲戒解雇を含む、さらに重い処分を受ける可能性があります。報告後は、会社の指示に従い、配置転換や休職などの措置を受け入れなければなりません。
自身の生活とキャリアへの影響を最小限に抑えるためにも、停止処分者講習を必ず受講し、一日でも早く業務に復帰できるよう努めることが重要です。免停期間中は、自身の運転習慣を見つめ直す機会と捉え、反省することが求められます。
2.会社としての対応策
ドライバーが免許停止になった際、会社は迅速かつ適切な対応を迫られます。
まずは就業規則に基づき、対象ドライバーへの処分(配置転換、休職、自宅待機など)を決定します。
同時に、運行管理者は代替ドライバーを手配し、配送スケジュールを調整するなど、事業への影響を最小化するための措置を講じなければなりません。
このような事態を未然に防ぐため、日頃からの安全教育の徹底が不可欠です。点呼時のアルコールチェックや健康状態の確認はもちろん、ドライブレコーダーの映像を活用した危険予知トレーニングや、無事故無違反ドライバーの表彰制度などを導入し、全社的に安全運転意識を高める取り組みが求められます。
会社ができるトラックドライバーの免停を防ぐ方法
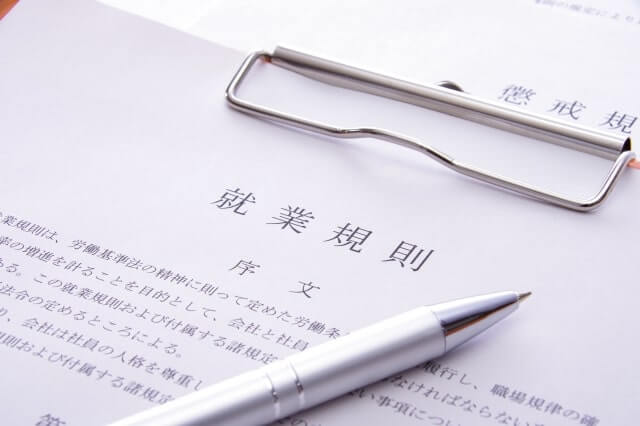
会社としてドライバーの免許停止に対応するためには、事前の備えが極めて重要です。組織全体で取り組むべき予防策を紹介します。
就業規則で処遇を明確に定める
まず、就業規則に「免許停止になった場合の処遇」について明確な規定を設けておく必要があります。これには、業務中の違反か私生活での違反か、違反の悪質性、ドライバーの普段の勤務態度などを考慮した処分内容(けん責、減給、出勤停止、配置転換、解雇など)を具体的に定めておきます。規定がなければ、処分の妥当性を巡ってトラブルに発展する可能性があります。
運行管理と勤務時間の適正化
免停の大きな要因の一つは過労や長時間労働による違反や事故です。
会社では、国土交通省が定める「改善基準告示」に基づいて、連続運転時間や休憩時間、拘束時間を適正に管理してください。
無理な運行計画を立てず、十分な休息を取れるよう調整することがドライバーの健康を守り、違反や事故のリスクを減らします。
点呼やアルコールチェックと安全教育の徹底
点呼やアルコールチェックといった基本的な安全管理の徹底です。
乗務前後の点呼で体調や車両の状態を確認し、アルコール検知器を使って飲酒運転を防ぐ仕組みを整えましょう。
また、定期的な安全運転研修の実施や、全ドライバーの運転記録証明書を定期的に取得して違反状況を把握することも有効な対策となります。
こうした取り組みを継続することで、ドライバー一人ひとりの安全意識を高め、免停リスクの回避につながります。
免停時の違反金と罰金とは
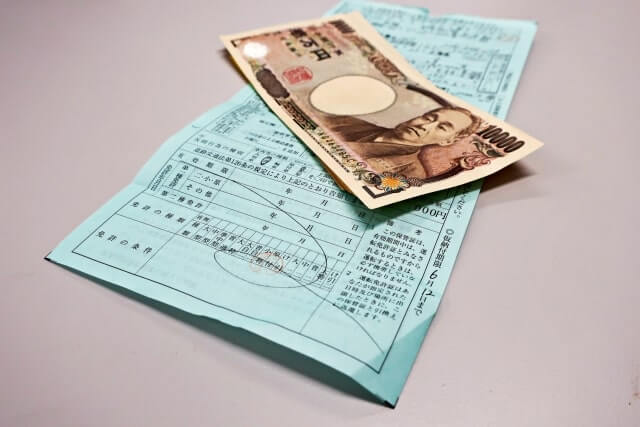
免停になると「罰金を払うのか?」と誤解されがちですが、正しくは 違反内容によって「反則金」または「罰金」 が科されます。
違反金と罰金の違いは、次のとおりです。
| 違反金 | 罰金 | |
| 概要 | ・比較的軽い違反に適用されるもので、行政処分の一種 ・支払いをすれば裁判にかからずに手続きが終了する |
・重大な違反に対して科される刑事罰 ・簡易裁判を経て前科が付く |
| 費用の目安 | 数千円〜数万円 | 数十万円に及ぶ |
トラックの主な違反ごとの反則金と罰金の目安は、表のとおりです。免停につながる重大違反では、反則金ではなく罰金が科される点にご注意ください。
| 違反内容 | 区分 | 金額の目安 |
| 速度超過(15〜20km/h未満) | 反則金 | 12,000円 |
| 速度超過(20〜25km/h未満) | 18,000円 | |
| 速度超過(25〜30km/h未満) | 25,000円 | |
| 速度超過(30km/h以上) | 罰金 | 5〜10万円 |
| 携帯電話使用(保持) | 反則金 | 18,000円 |
| 信号無視 | 12,000円 | |
| 酒気帯び運転(0.15〜0.25mg/L未満) | 罰金 | 約30万円 |
| 酒気帯び運転(0.25mg/L以上) | 約50万円 | |
| 酒酔い運転 | 100万円以下(+懲役刑の可能性) | |
| 無免許運転 | 50万円以下(+懲役刑の可能性) | |
| ひき逃げ(救護義務違反) | 100万円以下(+懲役刑の可能性) |
免停後(免許停止後)の流れ
免許停止が決定すると、ドライバーは警察から通知を受け取り、その後に免停処分が正式に始まります。
ただちに運転ができなくなるわけではなく、通知書が届き、指定された日に出頭して免許証を提出した時点から処分がスタートします。
免停後の流れを正しく理解しておき、仕事やの影響を最小限におさえましょう。
免停処分の通知書が届く
免停になった後、警察から免停処分を通知するハガキが届くのが一般的です。通知書が届くまでの期間は、違反内容によって数週間から1ヶ月程度かかる場合があります。
このハガキには「運転免許行政処分出頭通知書」と「意見の聴取通知書」の2種類があります。
| ・運転免許行政処分出頭通知書:累積点数が免停処分に達し、停止期間が90日未満の人に送付される ・意見の聴取通知書:90日以上の免停や免許取消など、より重い処分が予定されている人に送付される |
この通知書を受け取った場合、意見の聴取の場で、違反に関する状況や自身の意見を述べ、有利な証拠を提出する機会が与えられます。
これにより、必ずしも処分の軽減や免除がされるわけではありませんが、処分内容が変更されたり、停止期間が短縮されたりする可能性もあります。
出頭と免停開始
免停処分は、指定された免許センターなどに出頭し、免許証を提出した時点から開始されます。そのため、通知書に記載された出頭日時以降は運転できません。出頭の際は、車を運転して行かないよう注意しましょう。
違反者講習を受けられる場合も
免停のケースによっては「違反者講習」を受講できる場合があります。
この講習は、停止期間を短縮するものではなく、受講して優秀な成績を収めた場合に限り、免停処分そのものを回避できる制度です。
累積点数も計算から除外されるため、再スタートのチャンスとなります。
ただし、講習日当日は停止処分期間のため、日付が変わるまでは運転できません。
免停が原因のトラブル事例

免許停止が原因で発生するトラブルは少なくありません。最も多いのが、免停になったことを会社に報告せず、無免許の状態で運転を続けてしまうケースです。
これは発覚すれば懲戒解雇は免れず、万が一事故を起こせば極めて重い刑事罰と民事上の損害賠償責任を負うことになります。
また、プライベートでの違反による免停を会社に隠し、業務に支障をきたす事例もあります。
例えば、通勤ができなくなり遅刻や欠勤が増えたり、配送業務の直前になって運転できないことが発覚したりすると、結果的に会社からの信用を完全に失う事態につながります。
正直に報告し、誠実に対応することが、トラブルを避ける唯一の方法です。
トラックドライバーの免停に関するよくある質問

ここでは、トラックドライバーや運送事業者が抱える免許停止に関する疑問について、よくある質問とその回答をまとめました。
免停の期間を短くする方法はある?
免許停止の期間を短縮するための公式な制度として、講習の受講があります。すでに免停処分が確定した人は「停止処分者講習」を受けることで、処分期間を短縮できます。短縮日数は講習後の試験成績によって決まります。
また、軽微な違反を繰り返して累積点数が6点になった段階で「違反者講習」の通知が届いた場合は、この講習を受けることで、本来受けるはずだった30日間の免停にされずに行政処分が終了します。この制度は、過去3年以内に免停などの処分歴がない場合に適用される救済措置です
いずれの講習も、早期の業務復帰を目指す上では非常に有効な手段となります。
免停通知はいつ届く?
免許停止の対象となった場合に送られてくる「出頭要請通知書」は、最後の交通違反による取り締まりを受けた日から、数週間から1ヶ月程度で届くのが一般的です。
ただし、これはあくまで目安であり、違反の内容や警察の事務処理の状況によって前後することがあります。
例えば、オービスによる速度違反の検知など、違反者の特定に時間がかかるケースでは、通知が届くまでさらに時間を要する場合もあります。オービスによる速度違反の場合、通知は1週間から1ヶ月程度で届くという情報もあります。
通知書には、免停期間や違反点数、出頭すべき日時と場所などが記載されているため、届いたら必ず内容を詳細に確認することが重要です。
免停処分中でも原付や別の車種は運転できますか?
免停は「免許証そのものの効力」が停止される処分です。そのため、普通免許を持っているドライバーが免停になった場合は、トラックだけでなく原付や自家用車など、免許で運転できるすべての車種を運転することができません。
「トラックは運転できないが、原付なら大丈夫」と考える人もいますが、それは誤解です。免許証が停止されている状態で運転すれば、無免許運転と同じ扱いになり、さらに重い罰則を受ける可能性があります。
免停期間中は、たとえ短距離の移動であっても、いかなる車両も運転できない点に注意が必要です。
累積点数はネットやスマホで確認できますか?
累積点数は、自分がどのくらい違反点数を持っているのかを把握するうえで重要です。現在のところ、警察庁や都道府県の運転免許センターの窓口で確認できます。
一部の地域では、「運転免許証番号を用いたオンライン確認サービス」や、スマートフォンを使った情報照会が段階的に導入されています。
ただし、全国的に統一されたシステムではないため、居住地によってはネットでの確認ができない場合もあります。
確実に点数を確認したい場合は、最寄りの免許センターや警察署に直接問い合わせてください。
特にトラックドライバーの場合は、免停や取消に直結する可能性があるため、定期的に累積点数を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
免停は、違反後すぐなるものではありません。出頭要請の通知が来るまでの間は運転することが可能です。しかし、通知を無視して運転を続ければ、さらに重たい刑罰が科せられます。この点を踏まえると講習に行かないことはデメリットしかありません。
免停が確定したときは、なるべく決められた日に講習を受けましょう。そして、交通法規を再確認したうえで安全運転への意識を持ち、再び信頼と安全性を持って運転することに努めましょう。
-
- 免停中は運転ができず、制約を受けることになる
- 前歴によって免停点数や免停期間が異なる免停後には講習を受けることが必要
- 講習は安全運転意識の向上や交通法規の再確認する






