1ナンバー車の条件・税金・保険の維持費|3ナンバーとの違い

1ナンバー車は普通貨物自動車に分類され、主に荷物の運送に用いられる車両です。一方で3ナンバー車は普通乗用自動車に分類され、乗車定員10人以下の車両が該当します。両者の違いは用途にあり、1ナンバー車は貨物、3ナンバー車は人の輸送を目的としていることです。
本記事では、1ナンバー車の定義や特徴、他のナンバーとの違い、メリットデメリットを解説します。
目次
1ナンバー車とは?特徴

1ナンバー車は、普通貨物自動車として登録された車両です。
ナンバープレートの左側にある数字が「1」で始まることから、この名称で呼ばれています。
外見はSUVやワンボックスカーなどの一般乗用車と似ていても、用途区分が「貨物」となっているため、税金や保険、車検期間などが乗用車(3ナンバー)や小型貨物(4ナンバー)と異なります。
1ナンバー登録される車の多くは、ランドクルーザーなどの大型SUVやバン型車両で、車両サイズや用途が貨物基準に合致していることが条件です。
ナンバープレートの数字の意味
車両が国内の公道を走行するには、ナンバープレートが必要です。車両登録情報が参照できるようそれぞれのナンバープレートには、4桁の車両番号が表示されています。これらの番号は、盗難車両や交通違反車両の取り締まり時に、車両特定をおこなうために使用される重要な番号です。
4桁で表示される車両番号の他にも、ナンバープレートには、2〜3桁の「分類番号」が表示されています。分類番号には0〜9までの10の数字が用いられ、以下の通り、それぞれ該当車両が異なります。
1ナンバー車は、1で始まる2〜3桁の分類番号がついている普通貨物車のことです。
【※記事の表とナンバー表をそのまま使用する】
1ナンバーに分類される車両条件
1ナンバー車(普通貨物自動車)に分類されるには、次の条件を満たす必要があります。
| ・サイズが、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0mのいずれかを超えている ・荷物を積載するスペースの面積が1㎡以上で、座席部分よりも広い ・最大乗員重量よりも積載重量が大きい ・積載スペースの開口面積が縦80cm×横80cm以上 |
これらを満たしたうえで、陸運局にて貨物登録の手続きをおこなうことで、1ナンバーとして登録されます。
1ナンバー車は普通免許で運転可能?
1ナンバーの車は、普通自動車免許で運転できる条件とできない条件があります。運転できる条件は、免許を取得した時期によって異なります。
2017年3月12日以降に普通自動車免許を取得された方は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満、乗車定員10名以下の車であれば運転が可能です。
これは普通貨物自動車に分類されるナンバーの車であり、一般的には普通貨物と呼ばれることもあります。
一方、それ以前に免許を取得された方は、車両総重量5.0トン未満、最大積載量3.0トン未満、定員10名以下の車まで運転が可能です。
このように、取得時期によって運転できる車の条件が異なるため、ご自身の免許で運転可能な車かどうかを1日単位で確認する必要があります。該当する車が中型や大型の基準を満たす場合は、それぞれの免許を取得していなければ運転できません。
1ナンバーと4ナンバーとの違い

トラックの分類番号は、1ナンバーと4ナンバーの主に2種類です。4ナンバーは、車両サイズが小さいトラックに割り当てられます。
ここでは、1ナンバーと比較されることの多い4ナンバーとの違いを詳しく見ていきましょう。
車両サイズ
1ナンバー車が普通貨物自動車に分類されるのに対し、4ナンバー車は小型貨物車や軽貨物車に適用されます。最大積載量の制限はないため、積載量が3トンのトラックなども4ナンバーでの登録が可能です。
1ナンバーと4ナンバーは、登録車両サイズに条件があるので以下の表で確認しておきましょう。
| 車両の長さ | 車両の幅 | 車両の高さ | |
| 1ナンバー | 12m以下 | 2.5m以下 | 3.8m以下 |
| 4ナンバー | 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.0m以下 |
自動車税
1ナンバーと4ナンバーは、税金の計算方法が異なります。1ナンバーは、排気量に応じて課税されるのに対し、4ナンバーは最大積載量に応じて課税されます。
そのため、同じ排気量のエンジンを搭載していても、4ナンバーのほうが自動車税は安くなるケースが多くなります。
| 課税基準 | 年間税額(例) | 税負担の傾向 | |
| 1ナンバー | 排気量 | 3,000cc超:約51,000円 | 排気量が大きい車は高額 |
| 4ナンバー | 最大積載量 | 1t未満:約8,000〜16,000円 | 積載量が少ないほど安い |
車検費用
トラックの維持費用を考える際、車検の有効期間や自賠責保険、税金などの費用は重要なポイントです。車検の有効期間は、ナンバープレートの区分ではなく、トラックの重量によって異なります。
1ナンバーと4ナンバーは、車検の有効期間や費用構成に違いがあります。
どちらも新車登録から最初の車検までは2年ですが、その後は毎年車検が必要です。
ただし、4ナンバーは車両重量が比較的軽く、重量税や整備費用が安く済む傾向があります。一方、1ナンバーは車両重量やサイズが大きいため、整備費用や税負担が高くなりやすいです。
| 車検有効期間 | 車検費用の目安 | |
| 1ナンバー | 新車登録から2年、以降は毎年 | 約8万〜15万円 |
| 4ナンバー | 約6万〜10万円 |
1ナンバーでも車両総重量が8トン以上の場合には、初回から有効期間が1年間となります。
| 初回車検時の有効期間 | 初回以降の車検有効期間 | |
| 車両総重量8t以上 | 1年 | 1年 |
| 車両総重量8t未満 | 2年 | 1年 |
| 軽自動車 | 2年 | 2年 |
自賠責保険
自賠責保険料は、最大積載量によって金額が異なります。具体的には、最大積載量が2トンを超えるか否かで保険料が分けられています。
これは、積載量が多い車両ほど事故時の損害が大きくなるリスクがあるためです。
1ナンバーは、車両総重量や積載能力が大きいため、保険料がやや高く設定されています。一方、4ナンバーは、軽量小型のため、保険料は比較的安くなります。どちらも毎年車検時に1年分をまとめて支払うケースが多いです。
| 保険料の目安(12か月) | |
| 1ナンバー | 約18,000〜20,000円 |
| 4ナンバー | 約15,000〜17,000円 |
任意保険
1ナンバーと4ナンバーでは、任意保険の区分や保険料の計算方法が異なります。任意保険は、自家用乗用車とは異なり「自家用貨物車」区分で契約されるため、保険会社によって料率や補償条件が変わります。
特に1ナンバーは、車両サイズや用途によっては商用利用とみなされ、保険料が高い傾向です。一方、4ナンバーは小型貨物区分で比較的保険料が安く設定されるケースが多いです。
| 保険料の目安(年間) | |
| 1ナンバー | 約7万〜15万円 |
| 4ナンバー | 約5万〜10万円 |
高速料金
高速道路の料金は、車両のサイズによって異なります。一般的に、中型車や大型車に分類される1ナンバー車は、4ナンバー車と比較して料金が高くなる傾向があります。
荷物の量がそれほど多くなく、高速道路を頻繁に利用する場合は、4ナンバー車の利用が適していると考えられます。
参考として東名高速道路の東京ICから阪神高速の梅田ICまでの料金の一例を示します。
| 高速道路車種区分 | ナンバー区分 | 料金 |
| 軽自動車 | 4ナンバー | 10,080円 |
| 普通車 | 4ナンバー | 12,460円 |
| 中型車 | 1ナンバー | 14,860円 |
| 大型車 | 1ナンバー | 20,300円 |
| 特大車 | 1ナンバー | 33,760円 |
1ナンバーと3ナンバーとの違い
1ナンバーと3ナンバーの車には、税金や車検、保険といった維持費に大きな違いがあります。これらを比較すると、車両の用途や分類によって費用が大きく異なることが分かります。
ご自身のライフスタイルや車の使い方に合った選択をするためにも、それぞれの費用項目を詳しく見ていくことが重要です。
車両サイズ
1ナンバー車と3ナンバー車では、車両のサイズに関する定義が異なります。
1ナンバー車は、全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0mのいずれか、または排気量2,000ccを超える貨物車です。
車両は、貨物車として「積載量」を重視した構造になっており、荷室の広さや積載性能が優先されます。
一方、3ナンバー車は、これらのサイズ基準のいずれか一つでも超える乗用車に適用されます。乗用車としての「快適性や居住性」が重視され、積載量の基準はありません。
| 設計基準 | 車両構造の特徴 | 向いている用途 | |
| 1ナンバー | 貨物の積載性能を重視 | 荷室が広く、床面がフラットで耐荷重も高い | 業務用運搬、大型アウトドア用品の運搬 |
| 3ナンバー | 乗員の快適性を重視 | 座席や内装が充実し、静粛性・乗り心地が高い | 家族乗用、長距離ドライブ |
自動車税
車を所有すると毎年課せられる自動車税は、車の種類によって税額が変わります。3ナンバーの乗用車は排気量に応じて税額が上がる累進課税が適用されますが、1ナンバーの車税は最大積載量によって税額が決定されます。
そのため、3ナンバーの自動車より排気量が大きいにも関わらず、1ナンバーの自動車の方が自動車税は安価になる傾向があります。この違いは、乗用車と貨物車という自動車の用途の違いに基づいています。
| 年間税額(例:3,000cc超) | |
| 1ナンバー | 約16,000〜51,000円 |
| 3ナンバー | 約51,000円 |
車検費用
車検の費用は、車を維持する上で重要な項目の一つです。1ナンバーの車は、初回車検を除くと、その後は1年に1回の車検が義務付けられています。一方、3ナンバーの自動車は、初回とそれ以降も2年に1回の継続車検で済みます。
このため、車検の頻度が多いため、1ナンバーの車は3ナンバーの車に比べて、整備費用や事務手数料などの費用が多くかかります。また、車検時に支払う法定費用である自賠責保険料は、1ナンバーの車の方が3ナンバー車よりも高くなる傾向があり、特に最大積載量によって保険料が細かく分けられています。
| 車検有効期間 | 車検費用の目安 | |
| 1ナンバー | 新車2年、その後毎年 | 約8万〜15万円/年 |
| 3ナンバー | 新車3年、その後2年ごと | 約8万〜15万円/2年 |
自賠責保険
自賠責保険料は車検期間に応じて支払うため、車検サイクルが異なる1ナンバーと3ナンバーでは実質的な年間負担額に差が出ます。
保険料単価はほぼ同じですが、1ナンバーは毎年車検を受けるため、毎年1年分の保険料を支払うことになります。一方、3ナンバーは2年に1回まとめて支払うため、支払いタイミングが少なく済みます。
| 保険料の目安(12か月) | 支払いタイミング | |
| 1ナンバー | 約18,000〜20,000円 | 毎年 |
| 3ナンバー | 約17,000〜19,000円 | 2年ごと |
任意保険
1ナンバー車の任意保険は、3ナンバー車と比較して保険料が割高になる傾向があります。これは、1ナンバー車が「車」ではなく「自動車」として扱われるため、保険会社によっては加入条件が厳しく設定されているケースがあるためです。
車両のサイズや最大積載量、積載量などが考慮され、保険会社によっては5割ほど割高になることもあります。また、等級の引き継ぎができない場合や、運転者年齢条件などの割引が適用されないケースもあります。通販型の保険では、最大積載量に応じて加入できる車の制限がある場合や、車両保険を付けられないこともあるため注意が必要です。
相場は、次のとおりです。
| 保険料の目安(年間) | 契約区分 | |
| 1ナンバー | 約7万〜15万円 | 自家用貨物 |
| 3ナンバー | 約5万〜12万円 | 自家用乗用車 |
高速料金
高速道路の料金は、乗用車である3ナンバー車と貨物車である1ナンバー車で異なります。3ナンバー車は「普通車」区分が適用されますが、1ナンバーの車は「中型」区分に分類されるため、料金が割高になるのが特徴です。
この区分は、車の用途やサイズ、積載量などを総合的に考慮して決められており、1ナンバーの車は、高速道路の料金が3ナンバー車に比べて約2割増しとなります。そのため、頻繁に高速道路を利用する際は、料金を考慮して「車」の区分を検討しましょう。
| 高速料金区分 | 料金傾向 | |
| 1ナンバー | 中型車扱い | 普通車より約2割高い |
| 3ナンバー | 普通車扱い | 普通車と同額 |
1ナンバーのメリット・デメリット

1ナンバーのメリット
1ナンバー車は積載量が大きいというメリットがあります。これにより、一度に多くの荷物を運搬できるため、運送業務の効率を大幅に向上させることが可能です。
特に、大量の貨物を頻繁に輸送する事業者にとっては、積載量の大きさがもたらす作業効率の向上は、維持費の増加を上回る大きなメリットです。
さらに、自動車税は3ナンバーよりも安く設定されており、排気量が大きい車ほど節税効果が高いです。貨物車区分のため、構造変更の自由度も高く、荷台の加工や用途に応じたカスタマイズが比較的容易です。
1ナンバーのデメリット
1ナンバーには維持費や運用面での注意点があります。最大の負担は毎年の車検で、これに伴い自賠責保険や整備費用の支払いも毎年発生します。
さらに、高速道路では「中型車」または「大型車」区分になることが多く、長距離走行では3ナンバーよりも高速料金が割高です。
任意保険についても、自家用貨物扱いになるため料率が高く設定されることがあり、商用利用と見なされるケースではさらに上がる可能性があります。
1ナンバーに関する質問
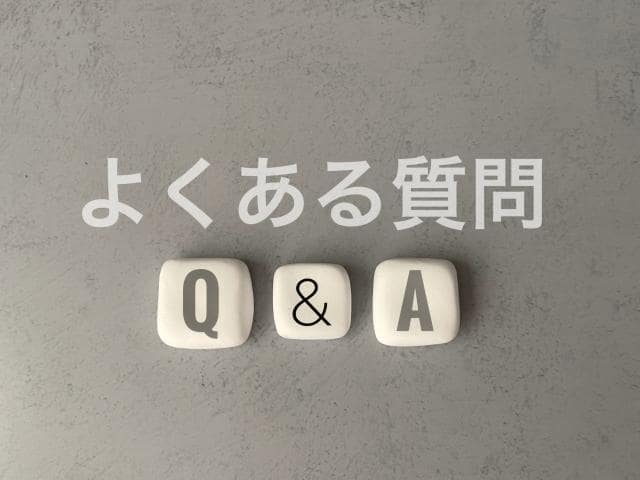
最後に、1ナンバーについてよくある質問と回答をまとめました。
1ナンバーの維持費用は高い?
1ナンバー車は、車両価格自体は用途やモデルによってさまざまですが、維持費は3ナンバーや4ナンバーに比べて高くなります。
主な理由は、毎年車検が必要であることと、高速料金や任意保険料が割高になることです。
例えば、年間の維持費には以下のような項目が含まれます。
|
・自動車税(3ナンバーより安いが排気量が大きいと総額は増える) |
趣味や仕事で積載性を重視する人にとってはメリットも大きいですが、維持費を抑えたい場合は事前に年間の総コストを計算しておくことが大切です。
1ナンバーの車へ変更するには?
3ナンバーの車を1ナンバーに変更するには、運輸支局で構造変更の手続きをおこなう必要があります。この変更にはいくつかの条件があり、まず車を貨物自動車として登録するための要件を満たさなければなりません。
例えば、多くのSUVやミニバンなどの乗用車では、車内の多人数乗車を想定したリクライニング可能なシートや、乗員スペースと荷室の間の隔壁などが変更の対象になります。
具体的には、荷物を積むスペースを確保するために3列目シートを撤去し、2列目シートのリクライニング機能を制限したり、荷室と乗員スペースの間に間仕切りを設けたりするなどの改造が必要です。
排気量が大きい大型の車やSUVであっても、これらの構造変更を行い、貨物車としての条件を満たすことができれば、1ナンバーへの変更が可能です。
改造が完了したら、運輸支局に車を持ち込み、車検に合格することで、正式に1ナンバーへと変更されます。維持費を抑える目的で変更を検討する方もいらっしゃいますが、改造費用や手間、そして年間車検となることなども考慮し、総合的に判断することが重要です。
1ナンバーの購入・買い替えはトラック流通センターまで

中古トラックの販売・買取をおこなっているトラック流通センターでは、1ナンバー4ナンバー車も取り扱っており、購入や買い替えの際にご利用いただけます。
トラック流通センターで中古車を購入するメリットは、豊富な在庫があることです。全国各地から中古トラックを集めているため、さまざまなメーカーや年式の車両を取り揃えています。
また、トラックの整備や点検も行っているため安心して購入いただけます。
以下リンクから詳細をご覧いただけます。ぜひ一度チェックしてみてください。
トラック流通センターかんたん問い合わせ
1ナンバー車両はこちら
4ナンバー車両はこちら
まとめ
この記事では、1ナンバーと4ナンバー、3ナンバーのそれぞれの特徴や維持費の違いを解説しました。貨物自動車の購入や利用を検討する際は、用途や積載量だけでなく、維持費用も考慮し、ご自身のニーズに合ったナンバー区分の車両を選びましょう。
-
- 1ナンバー車は、普通貨物自動車に分類され、車両サイズが大きいのが特徴
- 4ナンバー車は、小型貨物車や軽貨物車に分類され、車両サイズが比較的小さい
- 3ナンバー車は、3ナンバー車は、サイズ基準のいずれか一つでも超えると乗用車に適用される
- 1ナンバー車は他と比較すると、車検の有効期限が短く、自動車税や自賠責保険料、任意保険料、高速道路料金などの維持費が全体的に高くなる傾向がある






